財務書類について
貸借対照表
貸借対照表は、基準日(各年度末である3月31日)において、資産はどれだけあるのかを表左側に、また資産の源泉として、借入など将来負担を伴うもの(負債)とこれまでの税や補助金等で形成されたもの(純資産)に分類され、それぞれどのくらいあるのかを表右側に表記されます。これにより、資産保有状況と財源調達状況、つまり当該会計の財政状態を明確にすることができます。
また、資産は、一般的に長期に亘って保有するもの(固定資産)と短期的に現金化できるもの(流動資産)とに分類されます。さらに前者は、形のある有形固定資産(さらに道路、河川、公園や上下水道施設などのインフラ資産とその他の事業用資産に細分化)とソフトウエアなどの形のない無形固定資産、残1年以上の有価証券、貸付金、出資金や特定目的基金などの投資その他の資産に分類され、後者は、現金預金のほか、未収金、短期貸付金、財政調整のための基金が含まれます。
負債も、1年以上先に負担が発生するもの(固定負債)とそうでないもの(流動負債)に分類され、前者には、残1年以上の地方債や1年以内に戻入する各種引当金、後者には、1年以内に償還予定の地方債や賞与引当金が含まれます。
なお連結貸借対照表において、平成26年度より地方公営企業会計制度の見直しにより創設された補助金等の未償却分(繰延収益)については、統一的な基準の中で、固定負債に分類されています。
行政コスト計算書
行政コスト計算書は、一会計年度において、資産形成を伴わない主に経常的な支出とその経費に係るサービスへの対価として収受した収入(主に使用料・手数料)を対比し、そこから税収等で賄うべき行政コスト(経常的支出とその対価としての収入の差額:純経常行政コスト)を明確にすることができます。なお市税収入は、市民サービスに対する直接的な対価としてはとらえておらず、経常的支出のみならず、道路や公園などの公共資産形成的な支出へも資金投入しているため、ここでの収入には計上しません。
本表は、企業会計で作成する損益計算書に似ていますが、損益計算書は、一会計年度における当年度純利益を求めるのに対して、行政コスト計算書は、純経常行政コストを求める点で、相違があります。
本表では、経常費用として、業務に係る人件費、物件費のほか支払利息等を含んだ業務費用、補助金や他会計への繰出金など他組織へ支払う移転費用が含まれ、充当できる使用料・手数料を含む経常収益をそこから差引したものが純経常行政コスト、さらに災害復旧、資産除売却損などの臨時損失、資産売却益などの臨時利益を加えたものが純行政コストとして算出されます。
純資産変動計算書
純資産変動計算書は、一会計年度においての変動を表すもので、市税や地方交付税などの一般財源、国庫・府支出金などの特定財源に係る収入が増加要因として、行政コスト計算書で算出された純経常行政コストが減少要因として計上されます。
純資産の増加は、現役世代の負担により将来世代へ引き継がれる財産が増加した、あるいは将来世代の負担が減少したことを意味し、逆に純資産の減少は、現役世代が将来世代も利用可能な財産を消費してしまった、あるいは将来世代の負担が増加したことを意味します。
資金収支計算書
資金収支計算書は、一会計年度における現金等の資金の流れ(入出)について標記した表で、キャッシュフロー計算書ともいわれます。
市の所有する現金等については、市の経常的活動により発生する業務活動収支、公共施設の新増築や取得のほか、基金、貸付金の増減など市の資本形成活動により発生する投資活動収支、地方債の発行・償還など市の負債管理に係る財務活動収支の3つに分類され、 そこに、預り金などの市の所有に属さず、予算として計上されない現金(歳計外現金)の入出額が加えられます。
市税収入や地方交付税などのほか、固定資産取得に充当したもの以外の国府支出金などの収入、人件費や物件費、扶助費や補助金、他会計繰出金などの支出は主に業務活動収支に含まれます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 行財政管理課
電話:072-433-7267
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
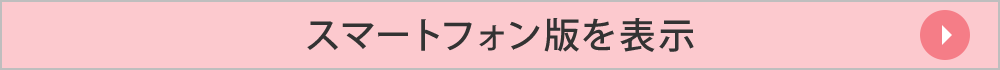








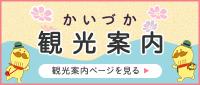
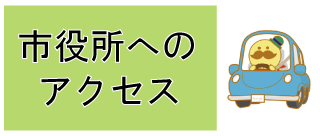

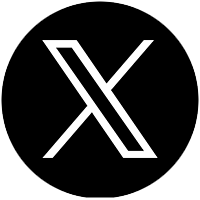


更新日:2018年03月30日