自主防災組織への助成
自主防災組織とは、地域のみなさんが、自主的に防災活動を行う組織です。大規模災害が発生したとき、みなさん自身が災害の初期段階で適切な防災活動を行うことにより、地域の人命救助や財産保護などに大きな力となり、災害による被害を最小限に抑えることができます。
役割
平常時の活動
- 防災意識の普及、啓発活動(防災に関する回覧板、防災研修の実施など)
- 被害の未然防止のための活動(建物・塀などの耐震診断など)
- 災害に備えて地域内を知る活動(避難誘導・介助の必要な方の把握や資機材管理など)
- 防災訓練(初期消火訓練、炊き出し訓練など)
災害時の活動
- 情報伝達活動(被害情報の収集・伝達など)
- 初期消火活動(消火器やバケツリレーなどでの消火活動)
- 救出救護活動(資機材を使っての救出や負傷者の救護など)
- 避難誘導活動(住民の安否確認、避難誘導)
- 物資分配活動(炊出しの実施及び配分)
結成時資機材助成
町会等で地域住民が自主的に組織する自主防災組織で、規約・計画等を定めている自主防災組織に対し、100万円分を限度として、資機材を助成します。
追加資機材等助成
令和4年度に制度を改正しました。
・自主防災組織が購入した資機材等の費用を、市が自主防災組織に現金で助成。(原則後払いとなります)
・助成を申請する際に、その年度に30万円一括か、10万円を3年間にまたがり助成を受けるかを選択することが可能です。
※30万円一括、10万円を3年間のどちらを選択しても3年後に次の助成の対象になり、再度選択することが可能となります。
※助成金は次年度に繰り越さない。
助成対象経費
1.自主防災組織が活動に必要な資機材を購入するための経費
2.災害時に必要なる備蓄品を購入するために経費
3.防災上必要な物品及び活動拠点を修繕するための経費
4.防災に必要な通信を行うための経費
5.災害情報を取得し、又は共有するためのシステムを構築し、又は維持管理するための経費
※助成対象の例
・防災機材(発電機、チェーンソーなど)
・防災用備蓄品(保存食、保存水など)
・防災物品や防災拠点(町会館等)の修繕費
・自主防災組織で使用する災害情報システム
※助成対象とならない例
・防災研修にかかる旅費、講師謝礼金、人件費
・事務用品費(鉛筆、コピー代、製本代など)
・器具借上料
・飲食費
申請の流れ
1.申請書等の提出(以下の書類を提出してください)
・助成金交付申請書
・助成金使用用途の概要書
・当該組織の規約及び役員名簿
2.交付決定通知書の受領
3.助成金使用用途の概要書に基づいて、購入・修繕を実施(※原則、交付決定通知書の受領前に購入等を行わないでください)
4.実績報告書、助成対象経費の内訳計算書、各領収書の写し、写真(単価が10万円を超えるもののみ)
5.助成金確定通知書の受領
6.助成金交付請求書の提出
7.助成金の口座振込
活動助成金
毎年度、自主防災組織が支出した対象経費の2分の1(5万円を上限)を助成します。
助成対象となる経費とは
- 燃料費、修理費、消耗品費など自主防災組織が管理する機材の維持に必要な経費。但し、資機材の保管場所の賃借料は対象外。
- 自主防災組織が行う防災訓練を実施するために必要な借上費、消耗品費、飲食費等の経費。但し、訓練目的以外に係る飲食費及び参加に係る人件費に相当するものは対象外。
- 防災知識を習得するために必要な講演会の講師謝礼金や研修会等に参加するための経費。但し、参加に係る人件費に相当するものは対象外。
- 災害時に必要と認められる食糧、飲料水その他備蓄物品を購入するための経費。
認めない経費の例
- 組織員に配布する記念品など購入費
- 組織員の飲食に関する経費(炊き出し訓練を除く)
- 組織員に対する日当などの人件費
- 社会通念上不適当な講師謝礼金
申請の流れ
1 申請書等の提出(以下の書類を提出して下さい。)
- 自主防災組織活動助成金交付申請書(様式第1号)
- 活動内容説明書(様式第2号)
- 対象経費の内訳計算書及び支出に係る領収書又はその写し
- 当該組織の規約及び役員名簿
2 助成金の請求
1 の申請書等を市で審査し、自主防災組織活動助成金交付決定通知書にて助成金の決定額をお知らせしますので、助成金の請求をして下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
危機管理部 危機管理課
電話:072-433-7392
ファックス:072-432-2482
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館3階
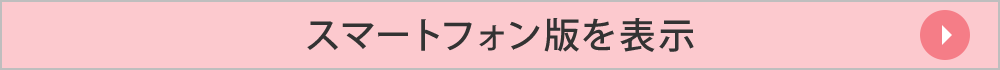








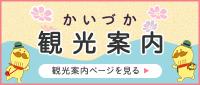
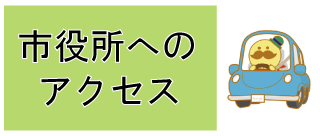

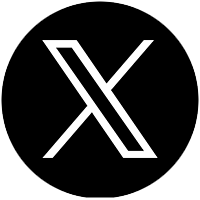


更新日:2023年09月04日