2,3ページ
代表質問
令和5年度市政運営方針に対して、3月1日から3日までの3日間、各会派代表者の5名の議員が行いました代表質問の一部を要約し、お知らせします。
貝塚ならではのまちづくりについて
<市民ネット貝塚>平岩 征樹
【問】地域ブランディングについて、水間寺周辺の取組みがあげられていますが、具体的に教えてください。
【答】旧水間街道沿いの旧工場をベーグルやコーヒーの販売を行う店舗と若者にも好まれるシンプルで洗練された家具や本を置いた休憩所に改修整備をしており、来訪者も地域の皆様もゆっくりと過ごせる仕掛けづくりを行います。
また、これから出店を予定しているかたや、新しい商品を販売したい事業者などが期間限定で出店できるチャレンジショップも併設します。旧水間会館についても改修整備し、水間寺周辺などの山手地域へ観光に訪れたかたの休憩所として運用します。
また、水間寺周辺において一体的に雰囲気づくりを行う必要があると考えており、地元町会や水間寺の皆様をはじめ地域のかたにご賛同・ご協力をいただく必要があることから、引き続き地域の皆様と意見交換を行ってまいります。これらの取組みは、地域とともに継続的に行っていくことが大切であり、徐々に来訪者を増やし、将来的には周辺の空き家や空き店舗を活用した店舗誘致に繋げたいと考えています。
【問】関係人口(地域と多様に関わる人々)を増やすためには、ふるさと納税を活用することが必要と考えますが、いかがですか。
【答】ふるさと納税の寄附者への返礼品として、地場産品に加え、体験型観光などを増やし、この地域でしか得られない体験を提供し、本市の魅力を直に感じていただきたいと考えています。
その上で、寄附者に対して地域の旬の情報を継続的に発信し、再訪を促すことで、持続的な関係を築き、関係人口の拡大を図ってまいります。
【問】ふるさと納税について、その総額を増やす取組みも大切だと考えますが、いかがですか。
【答】体験型観光などを増やしながら、事業者とともに新商品の開発も進め、積極的なPRを行い、総額を上げて第3次新生プランの効果額を達成できるように努めたいと考えています。
【問】新しい観光スタイルとありますが、どのようなものを想定されているのでしょうか。
【答】本市特産の農産物の収穫、調理および食事を通じ、自然や生活を体験するグリーンツーリズムや地場産業の工場を見学するツアーなど貝塚の魅力を深く感じられる独自性の高い、貝塚ならではの体験型観光を旅行会社、地元のかたと連携し、企画したいと考えています。
【その他の質問】
・市政運営について
・企業誘致と雇用創出について
・公共施設マネジメントについて
・防災対策について
・健康福祉の増進について
・子育てしやすいまちづくりについて
・持続可能なまちづくりについて
・地域医療提供体制について
・教育活動とその環境について
・財政運営について
南海貝塚駅周辺整備について
<自由市民>食野 雅由
【問】本市の玄関口である南海貝塚駅周辺についてお伺いします。ここは、長年未着手となっています。市政運営方針では本市の中心市街地として、にぎわいと魅力ある市街地環境の形成に努めるとされていますが、極めて高いハードルがあるのは誰もが認識するところであります。
市政運営方針に示された南海貝塚駅周辺の整備に、どのように取り組まれるのか、また、タイムスケジュールはどのように考えていますか。
【答】タイムスケジュールとしては、今の時代に合った居心地がよく市民のかたが憩えるまちづくりを実現するため、令和5年度より南海貝塚駅山側地区における既存の長期未着手の都市計画の見直しを進めてまいりたいと考えています。
見直しにあたっては、市民の皆様と対話を重ね、ニーズの把握を行った上で、利便性・快適性・安全性に配慮した道路や広場、公園などの都市基盤施設の整備を進めるための都市計画の変更案を作成し、大阪府との協議や本市都市計画審議会での審議を経て変更してまいります。
変更手続きの完了後は事業化に向けた調査や設計等を行ってまいります。
【問】南海貝塚駅周辺の南海本線の鉄道高架化について、以前質問した際、様々なハードルがあり、実現できる可能性が低いというご答弁をいただきました。実現できる可能性が低くても、必ず将来的に必要になると思いますので、目標は掲げておかないといけないと思います。
南海本線の高架化は、市長の選挙公約に掲げられていたと思いますが、いかがですか。
【答】選挙公約に南海本線の高架化は掲げていません。
【問】高架化してほしいという市民の思いがあるのは事実なので、ハードルが高いのはわかりますが、目標を掲げておくことは、できるのではないですか。
【答】高架ができれば、利便性も高くなるというのは当然承知していますが、事業主体が大阪府となります。大阪府が事業化検討の条件として示している、ピーク時の遮断時間が1時間のうち40分以上ある開かずの踏切や、自動車と歩行者の交通量が多く、渋滞や歩行者等の停滞が多く発生している踏切などの要件に該当する緊急対策踏切であることなどの条件をクリアしていないことから現時点での事業化は困難であると考えています。今、大阪府に要望しても検討もしていただけない状況です。
まずは、駅周辺のまちづくりを最優先で取り組んでまいります。
【その他の質問(抜粋)】
・将来ビジョンについて
・機構改革と権限移譲について
・市制施行80周年について
・ブランディング・シティプロモーション事業について
・観光振興ビジョンについて
・産業戦略について
・せんごくの杜について
・危機管理について
・子育てしやすいまちづくりについて
・地域公共交通計画について
・JR和泉橋本駅山側地区について
・水間鉄道について
・定住促進について
・水道事業について
・財政運営について
本市の観光振興を念頭に置いた府営二色の浜公園の指定管理者制度について
<新政クラブ>真利 一朗
【問】府営二色の浜公園について、新しい指定管理者からカフェレストランと売店、スケートパーク、グランピング施設などを展開すると発表がありました。オープンする日程を教えてください。
【答】デイキャンプ場を本年上半期に、カフェ・レストラン、売店およびスケートパークは本年下半期に、グランピング施設、バーベキューガーデンおよびオートキャンプ場は令和6年上半期にそれぞれ開業の予定と聞いています。
【問】20年間の指定管理の中で、新しい事業展開に関して市の要望を採用してもらえる可能性はあるのでしょうか。
【答】大阪府の府営公園管理要領に、指定管理者は地元市町村、企業、地域住民等と連携し、公園の利用促進を積極的に進めていくことと規定されています。指定管理者と連携、協議を行い、積極的な利用促進に協力してまいります。
【問】二色の浜海水浴場をきれいで安全な誰もが楽しめる優しいビーチとして、海辺の国際環境認証「ブルーフラッグ」の取得を目指すとあり、取得に関して、市も協力していくとあります。須磨海水浴場に次ぐ関西2番目、大阪府下で初めてのブルーフラッグを取得したビーチとなる可能性はあるのでしょうか。
【答】ブルーフラッグの基準項目は、ビーチの認証基準として、4分野33項目の基準があり、環境教育と情報分野で6つの基準、水質基準の分野で5つの基準、環境マネジメント分野で15の基準、安定性・サービス分野では7つの基準があります。
そのうち水質基準分野において、一般社団法人日本ブルーフラッグ協会のサポートを受け、昨年7月から8月にかけて、二色の浜海水浴場の事前の水質調査が行われ、基本となる水質はクリアしていると聞いています。二色の浜のイメージアップにより利用客や観光客の増加が見込まれることから、今後全ての基準を満たし、ブルーフラッグの取得が可能となるよう、地元との調整や海岸美化など必要な支援、協力をしてまいります。
【問】一番難関である水質基準をクリアできたということで、例えばごみ箱を設置するなど、他に普段からできることもあると思います。
また、一度基準をクリアしたからと安心せず、継続できるようにする必要があると思いますが、いかがですか。
【答】観光振興を図るため、基準をクリアし、それを維持することが必要だと考えており、市も協力してまいります。
【その他の質問(抜粋)】
・市民説明会・意見交換会について
・機構改革について
・市制施行80周年記念事業について
・ブランディング・シティプロモーション事業について
・貝塚ファンクラブについて
・公共施設マネジメント事業について
・国際交流について
・災害時の備蓄物資について
・マイナンバーカードについて
・子ども相談課について
・JR東貝塚駅のバリアフリー化や周辺整備の進捗状況について
・空き家・空き地対策について
公共交通について
<大阪維新の会>中川 剛
【問】高齢者や障がい者にとって自由に外出できるということは、自立して生きていく上で極めて重要な条件です。かつては、同居家族などによって支えられてきましたが、単身世帯の増加などの世帯構成の変化に伴って困難になっており、大きな課題であると考えています。
例えば、バスの自動運転サービスとスマートフォンの予約乗車システムを確立し、情報を統合することにより、効率的な移動手段を確保することができます。さらに、南海本線、JR阪和線、水間鉄道などと連携し、電車からのライドシェアを組み合わせることにより、自家用車を使わなくても快適に暮らせるまちづくりをめざすことができると考えています。このように多様な交通手段をITで統合する「マース」の活用について、どのように考えていますか。
【答】「マース」は、地域住民や旅行者一人ひとりの移動単位でのニーズに対応して、複数の公共交通やその他の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決済などを一括で行うサービスであり、観光や医療などの目的地におけるサービスとも連携することにより、移動の利便性向上や地域の課題解決に繋がるものと考えています。
令和4年度末策定の立地適正化計画において、利便性の高い公共交通沿線に居住や都市機能を誘導し、公共交通を中心としたまちづくりを推進することとしており、公共交通と沿線施設の連携につきましては、水間鉄道と沿線温浴施設が連携した取組みを昨年始めたところです。
また、令和5年度に予定している地域公共交通計画の策定にあたっては、本市で運行を行う交通事業者にも計画策定委員として参画いただき、各交通事業者間の連携による移動の利便性向上についても、計画の中で検討する予定です。
今後も「マース」の概念に基づいた公共交通ネットワークの構築並びに公共交通沿線地域の活性化に取り組んでまいります。
【問】山手地区は、高齢化によって車で移動できないかたなど、買い物や通院時の交通手段が大きな課題となっています。
立地適正化計画で、居住や都市機能を公共交通の利便性の高い地域に誘導するということですが、山手地区などの居住誘導区域外の公共交通はどのように考えていますか。
【答】令和5年度の地域公共交通計画策定時に法定協議会においてオンデマンド交通など、地域に適した持続可能な公共交通のあり方について議論してまいります。
【その他の質問(抜粋)】
・市政運営に対する認識について
・デジタル田園都市国家構想について
・観光振興について
・産業戦略について
・国際交流について
・行政DXの推進について
・成年後見制度について
・出産や子育てにかかる経済的負担の軽減について
・将来を見据えた持続可能なまちづくりについて
・南海貝塚駅周辺整備について
・都市計画道路泉州山手線について
・教職員の働き方改革について
・小・中学校でのICTの活用について
教育行政について
<公明党議員団>谷口 美保子
【問】葛城小学校と第二中学校でのコミュニティ・スクールの検証を踏まえ、中央小学校に幼稚園も含めたコミュニティ・スクールを導入するとのことですが、参加されているかたから自分がどのように参加すればいいのかわからないという意見がありました。
今回、導入するにあたり、目的や内容を丁寧に説明する必要があると考えます。
私の地元では、地域のボランティアによる子ども食堂、麻生中キッズカフェを開催しています。多くの子どもたちが参加し、保護者のかたもボランティアに加わってくれており、このままコミュニティ・スクールの玄関口になるのではと考えます。
今後、メンバーの選定をどのようにされ、どのように運営していくのでしょうか。
【答】コミュニティ・スクールの学校運営協議会の委員は、学校運営協議会規則の規定により、教育委員会が委嘱しています。また、選定につきましては、対象学校の校長から意見を聴取するとあります。
これらを踏まえ、現在は地域学校協働活動推進員、PTA会長、学校の特色ある取組みへの協力者など学校に関わりの深いかた並びに対象学校の校長および教職員を委員として委嘱しています。
コミュニティ・スクールの目的は、「地域とともにある学校づくり」であることから、保護者や地域のかたが、より主体的に学校の教育活動に参画できるよう、学校運営協議会を中心に、地域と学校が連携・協働する体制の構築に努めてまいります。
【問】地域が育てる学校というのがコミュニティ・スクールだと思いますので、地域への広げ方はどのように考えているのかお聞かせください。
【答】先進校からお話を聞いたり、コミュニティ・スクールマイスターから話を聞くなどして、一緒に理解を深めながら、その次の段階で地域のかたにどう関わっていただくか、考えていきたいと思います。
【問】学校に入ってきて刃物を振り回すという事件があると、どうしても閉ざしてしまう部分が出て心配ですが、やはり地域に開かれた学校ということが叫ばれているので、地域のかたが関わりやすくなるように考えていただきたいと思いますが、いかがですか。
【答】開かれた学校として誰でも来てくださいというのはなかなか難しい世の中です。子どもたちのため、学校のためと言ってくださるかたもたくさんいらっしゃるので、もっと気軽に来ていただける方法を今後も考えたいと思います。 まずは、各学校において、どういった方法がいいのか、研究してまいります。
【その他の質問(抜粋)】
・デジタル田園都市国家構想について
・せんごくの杜の今後の利活用について
・地域防災力向上の取組みについて
・人権尊重のまちづくりについて
・地域共生社会の実現に向けての取組みについて
・高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりについて
・子育てしやすいまちづくりについて
・安全・快適な公共交通ネットワークの構築について
・都市計画マスタープランと都市計画道路泉州山手線について
一般質問から
3月6日に行われた一般質問のうち、その一部を要約し、お知らせします。
機構改革について
<無会派>出原 秀昭
【問】機構改革で、職員定数は、どうなるのでしょうか。
【答】機構改革だけではありませんが、職員定数は1,033人から1,050人の17人の増加となっています。
【問】市長は以前、岡山県倉敷市の防災対策の要職に就かれ真備町に対して様々な防災対策をされました。そういったところへ報酬を寄附することも可能です。
本市において行財政改革をしっかりと進めていくのであれば、市長自ら身を切る改革をする決意がないのかお聞かせください。
【答】昨年の3月議会で、まず退職金については提案させていただいて、議会の方でお認めいただいております。それから報酬2割カットに関しても、議会の方へ提案させていただいた後、議会の方で修正をかけられております。
【問】1年たった今、改めて、まずはトップである市長自らされるのか、お聞かせください。
【答】先ほどもご答弁いたしましたとおり、昨年3月議会で、私としてはもう既に提案させていただいております。
大阪府・大阪市の「カジノを中核とするIR(統合型リゾート)」の大阪への誘致と貝塚市政について
<無会派>明石 輝久
【問】ギャンブル依存症、社会的負担が生じるカジノは不要だと思います。カジノ中心の統合型リゾートについて、どのように考えていますか。
【答】大阪・関西および日本の魅力を創造・発信する絶好の機会であり、経済、観光などの面においてメリットが大きいと考えられます。懸念事項でもあるギャンブル依存症や治安・地域風俗環境などへの対策についても盛り込まれており、総合的に考えて、経済への波及や雇用創出、観光振興などの面において効果的であると考えています。
【問】情報があまりにも少ないので、大阪府に対し、きちんとした情報を出すように強く求めて欲しいと思いますが、いかがですか。
【答】大阪府・大阪市へは、こういった意見があるということをお伝えしてまいりたいと考えています。
【その他の質問(抜粋)】
・高すぎる国民健康保険料を引き下げ、社会保障の原則に従った制度への拡充について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
貝塚市議会事務局
電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階
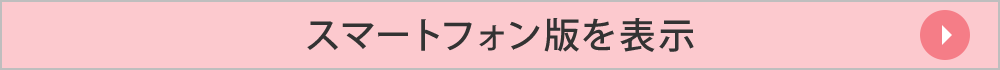








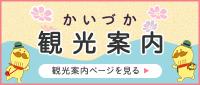
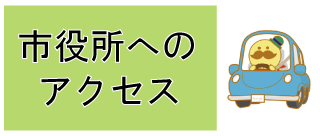

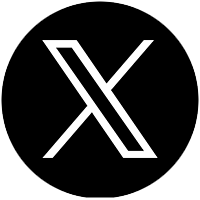


更新日:2023年05月02日