2,3ページ
一般質問
第3回定例会(9月6日、7日)に9名の議員が一般質問を行いました。その一部を要約し、お知らせします。
一般質問とは
◎テーマは自由
市政全般について、自由に質問することができます。
◎制限時間は60分
一人あたりの制限時間は、市からの答弁も含めて60分です。
◎質問形式は議員が選択
一問一答方式か一括質問方式を選択します。
質問項目は、本会議の約一週間前にホームページで公開しています。
傍聴やインターネット中継をご覧になる場合など、ご活用ください。
新型コロナウイルス感染症について
《自由市民》田中学
【問】市民のかたが、ワクチンの集団接種に来たときに、まず検温をして熱が37度5分以上あれば、すぐに結果がわかる簡易の抗原検査キットで検査をし、陽性なら市立貝塚病院の発熱外来に行ってもらって、再度きちっとPCR検査をするという水際対策が必要だと前回の6月定例会で質問させていただきましたが、現在の対応を教えてください。
【答】発熱者が来られた場合、まわりの人のリスクを考え、その場は速やかに帰っていただき、発熱外来を受診するよう案内し、翌日、連絡を取り受診状況等を確認しています。
【問】発熱したかたが自宅に帰ると家庭内感染のリスクがありますので、陽性者を早く見つけて感染が広がらないようにする必要があると思います。簡易の抗原検査キットであれば自分でもできますので、実施すべきだと思いますが、いかがですか。
【答】簡易なキットで抗原検査ができるということでしたら医師会と調整し、取り組んでいきたいと思います。
【問】今、各学校で感染者がたくさん出ています。緊急事態宣言などが出ている期間だけでも、毎週1回か2回、学校・幼稚園・保育所・市の窓口職場の職員・消防職員に対し、PCR検査や抗原検査をして、無症状の感染者がいないかを調べる必要があると思いますが、いかがですか。
【答】それらのかたについてはワクチン接種がかなり進んでいますので、定期的な検査につきましては、費用対効果等を考えながら検討してまいります。
【問】2回ワクチン接種をしても抗体ができなかったというかたもいらっしゃいます。抗体検査をしていないので、自分に抗体があるのかわかりません。命を守るために、早く検査をして早く封じ込めることが必要だと思いますが、いかがですか。
【答】市民対象の無料のPCR検査の準備を進めているところです。
【その他の質問】
・学校保健室の備品について
将来にわたって安心・安全の水を守る、貝塚市水道事業について
《無会派》明石輝久
【問】水道は命にかかわる重要なライフラインであり、市民生活に欠くことのできない事業です。
今、各自治体で運営している水道事業を大阪広域水道企業団に統合する動きが急速に進んでいます。事業統合について、現時点での市の考え方をお伺いします。
【答】大阪府では、今年4月までに13の市町村が大阪広域水道企業団と統合しています。貝塚市の水道水は府下43市町村中、4番目に安い料金で、今後もおいしくて安価な水道水を守っていこうと考えています。
また、現在貝塚市の水道は、津田浄水場の自己水と企業団からの受水が約半分ずつとなっています。この体制を守ることにより、地震等が発生した場合にも速やかに市民へ水道水を届けることができます。市民の生活を守ることが第一なので、今のところ統合に参加する必要はなく、事業統合の考えもありません。
【問】貝塚市の水道事業は水の安定供給、安価な水の市民への提供、また水質の確保など、これまでの技術の蓄積、職員の努力などが現在のレベルの高い事業を支え、保持していると考えます。
また、津田浄水場の全面改築を終えた今、貝塚市独自の優位性があります。現在の直営で進めることが重要だと考えますが、いかがですか。
【答】貝塚市の自己水は本市の宝物だと思います。自然からいただいている貴重な資源であり、これを守るために約30億円という莫大な投資をして、地震に強い水道施設の確立に向け取り組んでいるところです。この考えはこれからも堅持しますし、技術職員の確保も毎年必要に応じて採用しており、今後も市の直営で運営していきます。そのために人材確保、人材育成にも積極的に取り組んでいく考えです。
【その他の質問】
・高齢者の補聴器購入補助制度の創設について
・新型コロナウイルス感染症「第5波」から市民を守る緊急対策について
コロナ禍での貝塚市の取組みについて
《無会派》出原秀昭
【問】市役所のデジタル化について、昨年も質問させていただきましたが、部署を超えた横断的なチームの設置、また、デジタル化の専門事業者との協働や専門人材を登用してはと考えますが、いかがですか。
【答】現在、新技術を活用して地域課題を解決するスマートシティ基本構想の策定を進めており、スマートシティ推進委員会を今年6月に組織しました。また、当委員会には、分野ごとに関連部署の担当者で構成する横断的なワーキングチームを設置し、地域課題や新技術、法的根拠などを調査しています。また、ワーキングチームには、アドバイザリー業務委託先の専門人材3名や大阪府スマートシティ戦略部の職員も入っており、専門的見地からも調査・研究を行っています。
【問】デジタル化による市民の情報格差を減らす取組みも必要です。スマートフォン等の使い方を説明する市民向けの講座を公民館などで開催してはどうですか。
【答】山手及び浜手地区公民館、中央公民館では、スマートフォンの基本的な操作やLINEの活用などを学ぶ講座、ZOOMなどの使い方の勉強会を開催しています。
デジタル化を推進するに際し、情報格差の解消は重要課題だと考えており、スマートシティ推進委員会においても調査・研究してまいります。
【問】庁舎での新型コロナウイルス感染症対策として、サーモグラフィー型体温計の導入や窓口にアクリル板の設置など、更なる対策が必要ですが、いかがですか。
【答】窓口のカウンターにビニールを張るなど対策はしています。サーモグラフィー型体温計については、前向きに検討したいと思います。
【その他の質問】
・アフターコロナ時代の市立貝塚病院のあり方について
障がい者の雇用について
《公明党議員団》前園隆博
【問】今年4月、共生社会の実現を掲げた改正バリアフリー法が全面施行されました。障がい者や高齢者が交通機関をスムーズに利用できるよう事業者の取組みを明示したことで、心のバリアフリーに関する啓発事業を国が後押しすることも盛り込まれています。しかし、障がい者を取り巻く環境は依然として厳しいものがあります。9月は障がい者雇用支援月間です。これまでも障がい者の雇用の支援について訴えてきましたが、再度お伺いします。
就労継続支援A型事業所、同B型事業所などがあり、B型事業所は作業所とも呼ばれ、障がいのあるかたが何らかの作業を行い、工賃として収入を得ます。これに対してA型事業所は雇用契約を結びます。A型事業所は市内に1箇所しかありませんので、増やして欲しいという要望もあります。以前質問させていただいたときに、A型事業所が市内に複数あるほうが障がい者の選択肢が広がることから事業者の参入について働きかけるとありましたが、進捗状況はいかがでしょうか。
【答】事業所開設の相談があったときには、A型事業所が少ない状況を説明し、できるだけA型事業所を開設していただくよう働きかけを行っています。事業所の経営に関することで、強制はできませんが、今後も引き続き働きかけを行っていきたいと思います。
【問】B型は、工賃も安く交通費も出ません。A型と比べて工賃が非常に安いのは事実です。今後も引き続き工賃を増やす努力をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
【答】A型とB型のもともとの就労支援に対する目的等も違います。制度的なこともありますので、次期の計画を策定するときに全国的な動向も踏まえながら検討したいと考えています。
【その他の質問】
・子どもを事故から守る取組みについて
・大雨などによる土砂災害等からの避難について
小・中学校における新型コロナウイルス感染症対策について
《市民ネット貝塚》平岩征樹
【問】学校で子どもたちが新型コロナウイルスに感染した場合、学級・学年閉鎖や休校という対応になると思いますが、判断基準はありますか。
【答】学級・学年閉鎖や臨時休業については、大阪府教育庁作成のマニュアルの指示に従い、保健所の疫学調査により濃厚接触者やPCR検査対象者の状況などを踏まえながら検討し、教育委員会において判断しています。
【問】やむを得ず学校に登校できない児童・生徒に対するオンライン学習のほか、対面での学習が困難になった場合に備えて、家庭でのオンライン学習を組み合わせて進める必要があると思いますが、現状を教えてください。
【答】現在、学習支援アプリ「ロイロノート」を活用した学習を行っていますが、今後、ZOOMを使った自宅と学校の双方向での学習についても進めていく予定です。また、一人でタブレットの活用が難しい児童・生徒には、各家庭への学習教材の戸別配付等も併用しながら、学びが停滞しないように学習保障を進めてまいります。
【問】また、学校にウイルスを持ち込ませないために家庭との連携が欠かせません。家庭との連携について、取組みを教えてください。
【答】児童・生徒等に発熱や風邪等の症状が見られる場合には、無理せず登校を控えていただくようご協力をお願いしています。またその場合は、「欠席扱い」とはせず、「出席停止扱い」となることも重ねて周知しております。
他にも、登校前の検温や健康チェック、登校後の体調不良時の迎えなど、学校園が感染元とならないよう、2学期以降も各家庭との連携や協力依頼を引き続き行ってまいります。
通学路・生活道路の安全対策について
《新政クラブ》真利一朗
【問】先般、千葉県八街市の事故を受け、全国的に通学路の総点検の指示が出されましたが、本市では毎年定期的に市内幼稚園、小・中学校の通学路の危険箇所の点検を行っているのでしょうか。また、点検の結果、PTAや見守り隊のかたなどからの要望に対応されているのでしょうか。
【答】市・教育委員会・市内の学校園・警察署が連携して毎年継続して点検を行っております。また、各学校園及び各PTA等から報告のあった危険箇所の対策については、市・教育委員会・学校園・警察署等で組織する通学路安全推進会議において対策が必要な箇所の優先順位や対策方法について検討を行い、順次対策を実施しています。
【問】中央小学校正門前の通学路約800メートルが車の抜け道となっており、スピードを出す車が見られます。この区間にスクールゾーン表示が1箇所しかないので増やすことはできませんか。
【答】現地調査を行い、適切な場所へ早急に表示していきたいと思います。
【問】この区間に設置されている時速30キロ制限標識と駐車禁止標識の表示が消えかけています。早急に補修していただきたいのですが、いかがですか。
【答】警察の所管ですので、直接貝塚警察署に要望してまいります。
【問】この区間の車のスピードを抑制する対策として、ゾーン30の検討や、あえて車道を狭くしたりする1.5車線道路、路面に隆起を設けるハンプ等の交通安全対策ができないか、お伺いします。
【答】地域の主要な生活道路であることから、地元町会からの要望があれば、進めることができると思います。
【その他の質問】
・スケートボード場を含んだアーバンスポーツパークの誘致について
市道森阿間ヶ滝線について
《自由市民》籔内留治
【問】府営貝塚森住宅の建替えに際し、森町会から大阪府へ要望し、水間鉄道森駅前の道路拡幅が決定されました。進展がありませんが、大阪府からどのような報告を受けていますか。
【答】大阪府が関係地権者と協議を行っていますが、現時点で協議が調っておらず、事業の進捗が遅延しているとの報告を受けています。
【問】この道路は市が管理する市道です。市が拡幅に関与していただいて、市、大阪府、地元の3者でこの話を進めていただきたいのですが。
【答】地権者との交渉、費用負担は大阪府となっていますが、市も道路管理者であり地元をよく知る者の立場として、できるだけ積極的に関与していきたいと思います。
【問】次に、森駅前から府道40号(貝塚中央線)までの区間の道路について、東山のまちびらき以降、どんどん交通量が増えています。道路拡幅が必要だと思いますが、市の考えをお聞かせください。
【答】まずは交通量の多い水間鉄道森駅周辺の道路拡幅が最優先と考えています。また、道路拡幅の事業実施には用地買収費用を含む多大な事業費が必要なことから、国の交付金採択が不可欠であり、今後、大阪府による森駅周辺の道路拡幅工事が着手され、本事業に対する国の交付金採択のめどが立てば、事業化に向け検討を行ってまいります。
【問】道幅が広くなれば、歩道ができて安全対策ができます。事故があってからでは遅いと思いますが、いかがですか。
【答】この場所に限らず、児童・生徒の安全確保で歩道の要望は市内のいたる所であります。その中でもこの場所は、国からの特定財源の交付があれば市としても前に進めるものと思っています。
義務教育学校設置後の第五中学校の活用方法について
《市民ネット貝塚》阪口勇
【問】二色小学校と第五中学校を合体させた義務教育学校設置後、第五中学校の校舎は不要になると思いますが、その後の活用方法はどうなっていますか。
【答】第五中学校跡地の活用は、現時点で未定です。
【問】第五中学校は、避難所として重要な位置付けであり、南海トラフ地震が発生したときは校舎の3階へ避難するよう地域の避難計画にうたわれています。これらの機能をぜひ残して欲しいと考えますが、いかがですか。
【答】避難所の指定は継続する予定です。
【問】学校は、地域の財産でもあります。第五中学校では、体育館やグラウンドなどの校庭開放を行い、毎週少年野球やサッカー、バレーボールなど、子ども達や地域のかたが利用しています。地域コミュニティや地域福祉に寄与する利活用を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
【答】第五中学校の建物については、現在、部活動でも使用しており、小学校の体育館では手狭であることから、引き続き中学校の体育館を使用することも検討しています。子どもたちにとってより良い教育活動ができるよう、活用すべきであると考えています。また第五中学校跡地がこの先どうあるべきか、市全体のことも考え、検討してまいりたいと考えています。地域住民や子どもたちの幸せを思い、進めてまいります。
【問】地域の財産である学校の今後の活用について何が必要かを検討するうえで、地域の声をしっかりと聞いて検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
【答】これから様々な声をお聞きすることになると思います。そのような場を提供できるかどうかも含めて、検討したいと思います。
【その他の質問】
・週刊誌報道に伴う市政運営への影響について
二色の浜公園周辺の利便性向上について
《無会派》牛尾治朗
【問】府営二色の浜公園については、令和5年4月から新しい管理者による運営が始まる予定となっています。あの近隣は市が管理する市民の森などがあり、大阪府と協力して一元的な管理等も含めた合理的な利活用方針が必要と思いますが、いかがでしょうか。
【答】大阪府と協議を重ねた結果、大阪府が公募を行っている府営二色の浜公園の新指定管理者の募集要項の中に市民の森との連携が必要との記載があります。今後、新指定管理者が決まれば協議を進めたいと考えています。
【問】二色の浜公園内でもスケートボードパークを整備しようという動きが進んできています。例えば大阪府、貝塚市、新指定管理者が費用のいくらかを案分して整備し、管理運営は完全に地域のスケーターにお願いする方法もあり得るのかなと思っていますが、市として協力できる部分があるのかお伺いします。
【答】費用の分担は府営公園なので大阪府でお願いしたいと思いますが、スケートボードパークの実現に向け、大阪府と連携して進めたいと考えています。
【問】このエリアの利活用を進めていくと、当然交通量が増えます。これを機会に、大阪臨海線に向かう右折渋滞問題の解消について、何らかの整備を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
【答】渋滞の主な原因となっている府道大阪臨海線脇浜西交差点からパークタウン側にある市道二色大橋線二色一丁目交差点までの約60メートルの区間において、両側の歩道にある植栽部分を撤去し、大阪臨海線に向かう車道の1車線増設を計画しています。
協議が順調に進めば道路整備の完了は令和4年の秋頃を予定しています。
【その他の質問】
・幼児教育・保育の負担軽減について
・習い事などに使える教育バウチャー制度導入について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
貝塚市議会事務局
電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階
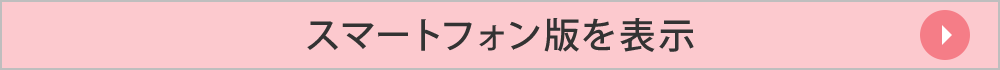








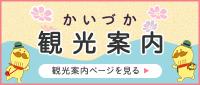
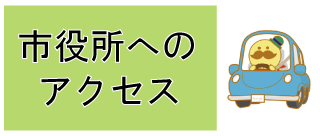

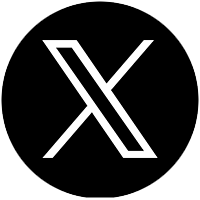


更新日:2021年11月05日