10ページ
ともに生きる
平和への思い
≪問合せ先≫人権政策課電話072‐433‐7160
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が今年のノーべル平和賞を受賞しました。
日本被団協は多くの被爆者証言を記録し、世論に働きかけ、さまざまな平和会議に代表団を送り続け、核兵器の廃絶を訴え続けてきました。これらの取組みがノーベル賞委員会に「核兵器のない世界を実現するための努力」と「核兵器が二度と使われてはならないことを目撃証言を通じて示してきたこと」として評価されました。
今も世界各地で紛争・戦争が発生し、住み慣れた土地を追われたり、命を落としたりする事態が起きています。「戦争」は決して他人ごとではなく、自分の問題として考えることが求められているのではないでしょうか。
市では、10月16日に広島から家族伝承者の方をお招きして「被爆体験家族伝承講話平和への思いを伝承する」をテーマにじんけんセミナーを開催しました。家族である被爆者から受け継いだ被爆体験や平和への思いを聴いて、改めて平和について考えるきっかけとなりました。
平和とは「争いがない」だけではなく、「差別をしない」「違いを認め合う」などを含めた概念です。世界がめざす「持続可能な開発目標」(SDGs)では、「平和と公正をすべての人に」と目標を掲げています。
一人ひとりが「平和」について考え、「平和」な世の中をめざして行動していくことが大切ではないでしょうか。
ハート交流館の願い
ハート交流館(青少年人権教育交流館)では、身近なことに平和を感じていただきたいとの思いから、毎年5月に市内の全小学校に声掛けをして「子どもまつり」を開催しています。
これは「子どもたちの、子どもたちによる、子どもたちのための」祭りです。祭りの日までは、司会は誰がするのか、舞台発表で何をするか、どんな店を出すかなど、祭り全体の企画を自分たちで考え、当日は、クラスメイトをはじめ、それまでに一度も会ったことがない人と仲間になり、一緒に祭りを盛り上げます。そこでは誰も傷つけあうことなく、笑顔で楽しい一日を過ごします。
子どもまつりを通じて、みんなで協力し、絆を深めあうことが平和への第一歩であると考えています。子どもたちが、仲間の一人ひとりを認め合い、尊重することの大切さを理解し、その思いを世界全体に広めてくれることを願っています。
≪問合せ先≫ハート交流館電話072‐432‐5959
フィールドワークの取組み
ひと・ふれあいセンターは、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点施設として、様々な講座やイベントなどを開催しています。
人権啓発活動の一環として、中学生を対象に東地区のフィールドワークを毎年実施しています。
市内でも太平洋戦争末期の昭和20年7月10日未明、東地区を含む市内6地区がアメリカ軍焼夷弾による空襲を受け大きな被害が出ました。この空襲で市内の犠牲者は20数人にのぼり、東地区では中心部の半分が消失し、16人が犠牲になった記録が残っています。
フィールドワークでは、空襲被害を写真などで説明し、当時の悲惨さや恐ろしさを中学生に伝えています。
子どもたちが、その現実を知ることで、平和の尊さを少しでも身近に感じてもらえればと願っています
≪問合せ先≫ひと・ふれあいセンター電話072‐422‐7523
市内小中学校における平和に関する取組み
市内の小・中・義務教育学校では、戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさを知ることで、一人ひとりが命の尊さを感じとったり、平和な世の中をつくるためにどうすればよいのかを改めて考えたりするために、平和学習を行っています。今回は、その中の2校の取組みについて紹介します。
6年生は、ピース大阪の見学を通して戦争や大阪大空襲についての学習を行いました。そして、8月の平和登校日には、全校集会で広島の平和記念式典の中継をリモートでつないで全員で黙とうをし、その後クラス単位で映像教材をもとに平和の尊さについて考え、自分たちの言動を見つめ直す機会をもつことができました。12月には、2年生・4年生を対象に聞いたことや考えたことについて報告会を行う予定です。
また、第一中学校の3年生は、今年度、核兵器廃絶を求める「高校生一万人署名活動」に参加しました。まず、修学旅行実行委員の生徒たちが、長崎県の高校生平和大使3人から活動内容や署名活動への思いをオンラインで聞き、全校集会でその話を伝えたり、各クラスの授業で語り合ったりしたうえで、校内での署名活動を行いました。そうして集まった署名を、修学旅行先の長崎で高校生平和大使に渡すことができました。
平和学習での学びを通して、これからも「平和な社会をつくっていくために自分ができることは何か」を自分ごととして考え、仲間とともに行動する力を身につけていけるよう取り組んでいきたいと考えています。
≪問合せ先≫学校教育課電話072-433-7108
平和に関するモニュメント
市役所緑の市民広場内に設置しているこれらのモニュメントは、皆様からの寄付などにより反戦・恒久平和への願いを込めて建立したものです。
平和祈念像はばたき(昭和62年8月設置)
1986年の国際平和年を記念し、戦争と平和・人権を考える貝塚市民のつどい実行委員会が設置。平和のシンボルのハトを形どった彫像と、市民により平和と人権尊重の願いが書き込まれた3,000枚以上のタイルが貼られています。タイルによる市民手づくりの像は、当時は全国的に大変めずらしいものでした。
瀕死の子を抱く母像(平成5年5月設置)
沖縄出身の彫刻家、金城実様による作品です。「戦争と平和・人権を考えるつどい」で講演会講師を務めたことをきっかけに貝塚市制施行50周年事業の一環として設置。ブロンズ芸術作品として恒久的に「人の生命と権利擁護」の大切さを訴えるモニュメントとなっています。
平和のともしび(平成7年8月設置)
戦争と平和・人権を考える貝塚市民のつどい実行委員会と世界人権宣言貝塚連絡会が、戦後50周年記念平和祈念事業として設置。折り鶴や合掌の姿をモチーフにデザインされています。台座内には設置に伴う様々な資料や、募金された方の名前を刻印したステンレス製プレートが収められ永久保存されています。
本市では、世界初の核被爆国として軍拡競争による惨禍を二度と繰り返すことがないよう非核三原則の堅持と軍縮を訴え核兵器廃絶・平和都市宣言を制定(昭和58年12月2日)しています 。
10ぺージの内容は以上で終わりです。広報かいづか令和6年12月号(No.1021)は全部で16ページです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 魅力づくり推進課 広報・シティプロモーション担当
電話:072-433-7059
ファックス:072-433-7233
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
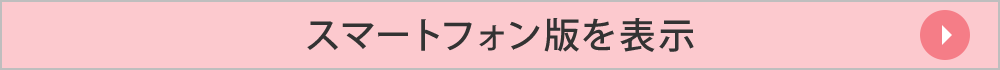








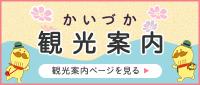
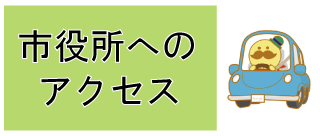

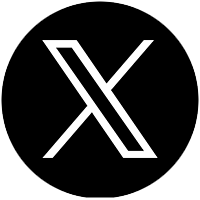


更新日:2024年12月04日