後期高齢者医療制度の給付
医療費が高額になったときは
同じ月に受診し、支払った保険適用医療費のうち、下記の自己負担限度額を超える部分が、申請によりあとから払い戻されます。一度申請されたかたは、以後発生した高額療養費が自動的に振り込まれます。
自己負担限度額
| 所得区分 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来 と 入院 (世帯単位) |
多数回該当 |
| 課税所得690万円以上 | 現役並み所得者3 | 252,600円 | 252,600円 | 140,100円 |
| 課税所得380万円以上 | 現役並み所得者2 | 167,400円 | 167,400円 | 93,000円 |
| 課税所得145万円以上 | 現役並み所得者1 | 80,100円 | 80,100円 | 44,400円 |
| 一般 | 一般 | 18,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | なし |
注意:現役並み所得者について
- 区分が現役並み所得者3の場合
総医療費が842,000円を超えたときは、超えた分の1パーセントを加算
- 区分が現役並み所得者2の場合
総医療費が558,000円を超えたときは、超えた分の1パーセントを加算
- 区分が現役並み所得者1の場合
総医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1パーセントを加算
注意:低所得者1・2について
- 低所得者2:住民税非課税世帯に属する被保険者
- 低所得者1:住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円となるかた。 ただし、公的年金等控除額は80万円として計算。 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者。
注意:過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
注意:75歳の誕生日月においては、誕生日前に加入していた医療保険制度(国保・被用者保険等)と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担限度額が、それぞれ本来の2分の1(半額)になります。
現役並み所得者1・2のかたは
現役並み所得者1・2に該当するかたで資格確認書(被保険者証)をお持ちのかたは事前に自己負担限度額等の適用区分の併記申請をして、病院へ提示することにより、医療費が区分上限以上、請求されることはありません。発行区分が不明な際は、保険年金課給付担当までお問い合わせください。なお、マイナ保険証をお持ちのかたは事前の申請は不要です。
申請手続き
資格確認書(被保険者証)を持参のうえ、下記窓口にて申請してください。
後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 253.5KB)
注意:医療機関で提示しなかった場合、「現役並み所得者3」の自己負担限度額が適用され、差額分を後日、高額療養費として払い戻します。
低所得者1・2のかたは
低所得者1・2に該当するかたで資格確認書(被保険者証)をお持ちのかたは事前に自己負担限度額等の適用区分の併記申請をして、病院へ提示することにより、医療費や入院時の食事代が安くなります。 発行区分が不明な際は、保険年金課給付担当までお問い合わせください。なお、マイナ保険証をお持ちのかたは事前の申請は不要です。
申請手続き
資格確認書(被保険者証)を持参のうえ、下記窓口にて申請してください。
後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル: 253.5KB)
注意:医療機関で提示しなかった場合、「一般」の自己負担限度額が適用され、差額分を後日、高額療養費として払い戻します。
入院時の食事代
| 所得区分 | 負担額(1食あたり) |
| 現役並み所得者・一般 | 510円(指定難病患者 300円) |
| 低所得者2(90日までの入院) | 240円 |
| 低所得者2(90日を超える入院)(別途申請必要) | 190円 |
| 低所得者1 | 110円 |
注意:低所得者2の認定を受けておられる方で、申請日以前の12か月で91日以上の入院がある方については、再度申請して長期入院該当の認定をうけることにより、入院時の食事代が91日目より1食あたり240円から190円にさらに減額されます。申請には、入院日数が91日以上あることが確認できる領収書等の提示が必要となります。
療養病床に入院するかたの食費・居住費
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
| 現役並所得者・一般 | 510円 | 370円 |
| 低所得者2 | 240円 | 370円 |
| 低所得者1 | 140円 | 370円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
- 低所得者1・低所得者2・老齢福祉年金受給者に該当するかたで資格確認書(被保険者証)をお持ちのかたは事前に自己負担限度額等の適用区分の併記申請をして、病院へ提示することが必要です。
- 療養病床に入院しているかたが対象です。(ただし、難病のかたは入院時食事療養標準負担額のみ負担します。また、入院医療の必要性の高いかたは入院時食事療養標準負担額のほか、居住費を負担します。)
- 指定難病の方や医療の必要性の高い方は、別途申請により「90日を超える入院」が適用されます。
- 現役並み所得者及び一般区分のかたのうち、指定難病の患者の入院時食事療養標準負担額は280円です。
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担の合算額が高額になるときは、申請に基づき、下記に設定される自己負担限度額を超える額が支給されます。
後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担限度額(年額)
| 所得区分 | 区分 | 自己負担限度額 |
| 課税所得690万円以上 | 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上 | 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上 | 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般 | 一般 | 56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者1 | 19万円 |
申請手続き
対象となるかたへは大阪府後期高齢者医療広域連合からお知らせします。お知らせが届きましたら広域連合へ申請をしてください。
医療費の払い戻し
医師が必要と認めたギプス・コルセットなどの医療用装具を購入し、費用の全額を自己負担した場合、下記窓口で申請していただき支給決定されれば、後日、一部負担金を差し引いた金額を支給します。ただし、費用を支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんのでご注意ください。
申請手続き
資格確認書(被保険者証)、医師の意見書、領収書、口座情報のわかるものを持参のうえ、下記窓口にて申請してください。
葬祭費
被保険者のかたがお亡くなりになったときは、葬祭を行ったかたに対し、葬祭費として50,000円を支給します。
葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請してください。
申請手続き
資格確認書(被保険者証)、葬儀の領収書、申請者の口座情報のわかるものを持参のうえ、下記窓口にて申請してください。
注意:領収書は葬儀を行ったかた、亡くなった方の姓名が記載されたものを持参してください。
交通事故にあったときは
交通事故など第三者による行為で負傷した場合でも後期高齢者医療制度の保険を利用して診療を受けることができます。(自損事故の場合も同様です)
すぐに警察に届けると同時に、下記窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
注意:交通事故が発生し、示談で済ませた場合、後期高齢者医療制度で診療を受けることができないことがあります。
保健事業
健康診査
生活習慣病の早期発見のため、被保険者を対象に健康診査を実施しています。被保険者には毎年4月中に、また、年度途中に新たに75歳になられるかたには、誕生日の翌月に大阪府後期高齢者医療広域連合から受診券をお送りします。
広域連合が指定する医療機関等において、受診券に記載された有効期限までに1回、無料で受診することができます。受診の際は、受診券と資格確認書(被保険者証)もしくはマイナ保険証を忘れずにお持ちください。
ただし、病院又は診療所に6ヶ月以上継続して入院中のかた、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居しているかたは健康診査の対象外となります。
注:退院・退所した場合は、受診券を発行いたしますので、お問い合せください。
歯科健康診査
歯や歯肉の状態、口腔衛生状態等をチェックし、口腔機能の低下や肺炎等を予防するため、被保険者を対象に歯科検診を実施しています。被保険者には毎年4月中に、また、年度途中に新たに75歳になられるかたには、誕生日の翌月に大阪府後期高齢者医療広域連合から歯科医院リストをお送りします。
広域連合が指定する歯科医院において、年度中(4月1日から翌年3月31日まで)に1回、無料で受診することができます。受診の際は、資格確認書(被保険者証)もしくはマイナ保険証を忘れずにお持ちください。
ただし、病院又は診療所に6ヶ月以上継続して入院中のかた、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居しているかた、介護予防事業における口腔ケア等の歯科保健事業の対象となるかたは歯科検診の対象外となります。
人間ドック
被保険者を対象に26,000円を限度として人間ドック受診費用の一部助成事業を実施しています。
申請手続き
申請については、保険年金課にて受け付けます。
人間ドックの領収書、検査結果通知書、資格確認書(被保険者証)、口座情報のわかるものをご持参ください。(口座振込にて後日支給されます)
注意:申請は、同じ年度で一回限りです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
メールフォームによるお問い合わせ
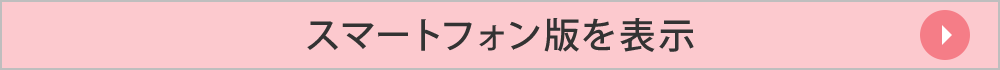








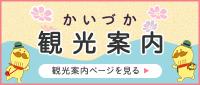
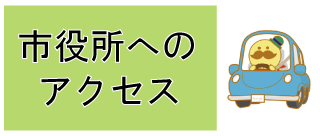

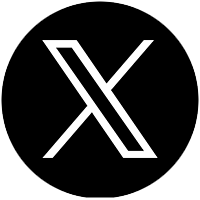


更新日:2025年04月01日