2,3ページ
代表質問
令和7年度市政運営方針等に対して、各会派代表の4名の議員が代表質問を行いましたので、その一部を要約し、お知らせします。
わかりやすい議会運営のため、一問一答式で質問できるようにしました。
≪自由市民≫出原秀昭
地域まちづくり協議会の設置について
- 【問】市は、市政運営方針に基づき予算や人的配置をし、それに基づき職員が施策を全うします。二元代表制のもとで対等な立場から質問しますので、明確な答弁をいただきたいと同時に、批判だけではなく、市政運営方針の中でどのようにノウハウを生かしていくのかということを提案型で質問させていただきますので、するかしないかお答えいただければと思います。
市長選挙の公約にまちづくりに関することが書かれており、それを市政運営方針に落とし込んでいます。市長はどのようなまちづくりを考えているのかお伺いします。
【答】令和7年度の市政運営方針に記載のとおりです。また、公約として選挙公報に掲載した項目については、順調に進捗していると捉えています。 - 【問】まちづくりの基本は、市民であり、市民協働、市民の自治参加が重要だと考えます。トップダウン型ではなく、町会・自治会、婦人会、老人会、NPOを含めた小学校区の地域まちづくり協議会を立ち上げて、既にある校区福祉委員会を巻き込んで進めていくべきだと考えています。その中で雇用も含め、ある程度の予算配分をして、校区単位のコミュニティをつくるべく条例化して進めるべきだと考えますが、いかがですか。
【答】市の方針を立てる中で、市民の皆様との危機感の共有、そして施策を一緒に進めていただくために、対話、意見交換が大事だと考え、策定プロセスにおいて市民の皆様への説明会、意見交換等を行いながら進めているところです。 - 【問】私が聞いているのは、町会・自治会や校区福祉委員会などを巻き込みながら、新しい公共の担い手として小学校区を単位とする地域まちづくり協議会をつくってはということですが、いかがですか。
【答】施策を実行する上で行政だけで完結するとは限りません。公民連携や広域連携など、いろんなステークホルダーと一緒になり、その施策を実行していくということです。
市立貝塚病院の経営状況について
- 【問】本市は直営で市立貝塚病院を経営し、市長が開設者となっていますが、今後の経営方針を含めて、存続のあり方をお伺いします。
【答】大阪府医療計画等で示された地域の中核的医療を担う基幹病院としての役割を果たすための最適な形態を予断を持たずに選択すべきと考えています。経営的には非常に厳しい状況ですが、経営強化プランの主たる目標である経常収支黒字化を計画期間内に達成できるよう、引き続き収益増加と費用削減に取り組んでまいります。 - 【問】市長の公約に、市立貝塚病院、水道等のインフラサービスなどよいものは維持し、さらに充実を図るとあります。市立貝塚病院は、存続ということでよろしいですか。
【答】市立貝塚病院の目的として大阪府医療計画等で示された地域の中核的医療を担う基幹病院としての役割を果たしていくということです。 - 【問】今の答弁では、指定管理にすると言っているようなものです。私は四半世紀公立病院に勤めていたので、わかります。市立病院を残すか、残さないか、お答えください。
【答】指定管理なのかその他の経営形態なのか、そういった形態については手段です。目的を果たすために最適な手段を予断を持たずに選択すべきものと考えています。 - 【問】市立貝塚病院は維持し、充実を図ると公約に書いていますが、指定管理も手段だからその可能性があるということですか。
【答】何度も申し上げますが、目的は大阪府医療計画等で示された地域の中核的医療を担う基幹病院としての役割をこれからも果たすということです。経営の形態がどうかというのは手段であって、それは予断を持たずに見極めていくべきものと考えています。
その他の質問
- ふるさと納税について
- 都市計画道路泉州山手線について
- 自然循環型Gx事業について
- 町会・自治会活動について
- 職員人事・人材確保について
- 地域包括ケアシステムについて
- 主要駅関連について
- 地域公共交通について
- 水間公園について
- 上下水道事業について
- 消防本部について
- 大阪・関西万博(子ども参加)について
《新政クラブ》南野敬介
貝塚市人権擁護に関する条例について
- 【問】人権課題が多様化する時代において、 30年前に制定された「貝塚市人権擁護に関する条例」を現在の課題に対応した内容に改正する必要があると考えますが、いかがですか。
【答】これまでも様々な人権問題解決に取り組んでまいりましたが、昨今のLGBTQ、インターネット上の人権侵害など、複雑・多様化する人権課題に対し、具体的な施策を進めるために「第2次人権行政基本方針」を策定しました。
現在のところ、人権課題を解決するための手段である条例の改正が必要であるか、市内部で精査中です。 - 【問】貝塚市として、この条例を今の時代に合わせたいという前提なのか、その辺のスタンスはどうですか。
【答】今の条例は、あらゆる差別に対応し、一番幅広いどんな言葉にも漏れがない規定となっています。より具体的に盛り込む必要があるかを含めて精査しています。 - 【問】人権に特化した意識調査を実施してはいかがですか。
【答】令和4年度に実施したのが直近で、その追跡の意味もありますので、その期間なども含め人権擁護審議会に諮った上で、意識調査を実施していきたいと思っています。 - 【問】人権行政を推進するため、人権擁護審議会を積極的に活用すべきと考えます。人権課題は、日常的に行政を進めていると必ずあると思いますので、人権擁護審議会を日常的に開催すべきと考えますが、いかがですか。
【答】意識調査の実施や条例の改正に関しても現在精査中で、その中身が固まりましたら、審議会にかける方向で進めています。人権行政の推進については、市もしっかりと進めていきたいと思っていますので、適宜開催ということが、毎年の開催につながることもあると考えています。
インターネット上の誹謗中傷等書き込み禁止条例の制定について
- 【問】法改正によりSNSをはじめとするインターネット上における差別・人権侵害の解消、被害を受けた方への救済支援の道筋が少しずつ広がってきていると感じています。まず、法改正に対する見解及び市民への周知方法をお示しください。
【答】本市では、差別事象の動画や書き込みを確認した場合は、速やかに大阪府へ報告を行い、大阪法務局並びに、SNSの運営事業者等に削除要請を行っています。今後も、大阪府と一層連携を図りながら、広報紙やホームページなどで市民に情報発信を行い、セミナーの開催などによりインターネットリテラシーの向上に取り組んでまいります。 - 【問】人の命を奪う、奪いかねない「表現の自由」はないと考えています。「インターネット上の誹謗中傷等書き込み禁止条例」を制定すべきと考えますが、いかがですか。
【答】現在もインターネット上の誹謗中傷等への対処につきましては、市条例によらずとも推し進められていることから、今後も条例の策定は考えておりません。 - 【問】貝塚市ではそれを許さないという姿勢を示す上でも、大切な意義のある条例だと思います。条例を制定することによって、注意喚起にもなると思います。また、人権や情報を守ってくれる、書き込みを制御してくれる、貝塚市はそうやって条例をつくって守ってくれるというのが、安心して暮らせる貝塚市をつくる一つだと考えますが、いかがですか。
【答】インターネット上の誹謗中傷等の対策を講じていくことが重要です。対策を講じていくために必要な条件整備として条例がいいのか、宣言がいいのか、その他の方法がいいのか、そこは手段ですので適切な手段を選択していくべきと考えています。
その他の質問
- 姉妹都市、友好都市の取組について
- せんごくの杜跡地について
- 公務内で職員個人が訴えられた時の対応について
- 避難所の考え方について
- 三館等施設統合について
- 本人通知制度について
- 犯罪被害者等支援条例の制定について
- 地球温暖化対策について
- 成年後見人制度について
- 子どもの権利条例の制定について
- 市営東団地住宅の住宅再編・整備計画について
- オンデマンド交通・路線バス運行について
- 学校の教職員の働き方改革について
- 2025年日本国際博覧会の小・中学生の学校行事としての見学について
- デジタル教科書について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》長谷川博文
学校教育環境について
- 【問】不登校等対策支援事業「かいづかSMILEプラン」について、本市の状況と、今後、どのように対策を進めるのかお伺いします。
【答】本市でも不登校児童生徒は年々増加しており、中でもスクールカウンセラー等の専門家や支援機関につなげることができていない子どもが約4割に達するなど、支援が行き届いていない現状があります。
不登校により学びにアクセスできない子どもをゼロにすることをめざし、全ての子どもたちが安心して学べる多様な支援環境を整備するため、「かいづかSMILEプラン」を推進してまいります。 - 【問】不登校児童生徒を多様な支援環境につなぐための手だてを教えてください。
【答】子どもや保護者が抱える悩みや不安に能動的にアプローチしていくシステムの構築が必要だと考えています。
心理や福祉の専門家が訪問支援やオンライン面談を通じて個々の状況を把握し、それぞれに適した支援策を提案していく予定をしています。 - 【問】「かいづかSMILEプラン」には、メタバースや遠隔操作ロボットなど子どもたちが興味を持ちそうな言葉が入っていますが、それに満足し、逆に不登校のきっかけになることも危惧されますが、いかがですか。
【答】メタバースや遠隔操作ロボットの活用による登校意欲の低下を防ぐため、心理や福祉の専門家であるアウトリーチ支援員が、対象児童生徒の状況やニーズを正確に把握した上で、適切な支援計画につなげていくことで対応できると考えています。 - 【問】新規不登校者を減らす対策は、どのように考えていますか。
【答】問題行動を減らすのではなく、望ましい行動を増やすことを目標に、子どもたちの頑張りや努力の過程を称賛・承認することで、自己肯定感や自己有用感を育み、学校がこれまで以上に居心地のよい場になるように努めてまいります。
府立高校との連携について
【問】本市にある府立貝塚高校と府立貝塚南高校は、大切な教育機関であることはもちろんですが、それ以上に貝塚市の地域において大切な存在です。
貝塚高校は、本市と連携し、農業の授業で、市庁舎横のプランターにコスモスの苗の植え付け、地域の幼稚園児を招待しての芋掘り、栽培した農産物や草花などを近隣の方々に販売するなどしています。また、貝塚南高校は、保護者との連携による地域清掃活動の実施や、警察署と連携した大阪府内唯一の高校生ボランティア団体の活動として、市内において、非行防止や犯罪被害防止を目的としたキャンペーンやイベント活動に参加しています。
高校生に地域社会との関わりを深めてもらうことで地元地域への理解や、さらに将来の地域を支える人材の育成につながることも期待されます。
地域交流や多世代交流、地域課題の解決につなげていけるような市内の府立高校との積極的な連携や情報交換などを進めていくべきだと考えますが、いかがですか。
【答】持続可能なまちづくりを進めていくためには、市とともに様々な地域団体が連携していくことが重要です。義務教育を終えた後、高校生や大学生が貝塚市に愛着を持ち、まちづくりにも参画してもらえるよう、市内府立高校との連携を積極的に進めていきたいと考えています。
両校とは、現在も様々な交流をしていますが、令和7年度からは、さらに連携を深めていくため、各社会教育関係課や施設から一緒にこんな取組をしていこうと案を提示しました。両校からは積極的に連携していきたいとの意向を伺っています。4月以降、調整が済んだものから実施してまいります。
その他の質問
- 大阪・関西万博について
- 姉妹都市・友好都市について
- 企業誘致計画について
- 外国人転入者について
- これからの人事戦略について
- 使用済食用油の回収について
- 動物愛護に関して
- フレイル予防について
- 学童保育や待機児童対策について
- 都市計画について
- 貝塚市における農業について
- 子どもの居場所について
- スポーツ振興について
- 南海トラフ地震に対する本市の備えについて
- 消防広域化について
- 市立貝塚病院の運営と今後の展望について
- 持続可能な水道事業について
《公明党議員団》谷口美保子
5歳児健診の導入について
- 【問】一人でも多くの子どもたちが適切な療育につながるよう5歳児健診は必要だと考えます。子育てしやすいまちづくりにおいて、就学前の子どもたちの育っていく環境を整えることは、大変重要だと思います。
委託先の医療機関と連携を密にし、情報共有することで、虐待等の予防や早期発見にもつながり、また、情報の活用などにより、伴走型相談支援の効果的な実施にもつなげることができます。5歳児健診導入のお考えをお聞かせください。
【答】5歳児健診は国の補助事業であり、令和10年度までに全国の自治体での実施をめざしています。実施にあたりこども家庭庁は、保健、医療、福祉、教育の各分野における地域のフォローアップ体制を充実させていくことを求めています。本市でも実施に向けた体制づくりを進めるため、医師会や関係機関と調整し、実施体制の確保に努めてまいります。 - 【問】早期の導入をお願いしたいと思いますが見込みはあるのでしょうか
【答】体制づくりが必要ですので、医師会の事情も考慮しながら実施時期について相談しながら進めてまいります。 - 【問】担当課を大きくするか、違う課と連携するか、その辺を考えないと5歳児健診を前に進めることが困難だと思いますが、いかがですか。
【答】取り組んでいかないといけない課題であると認識していますので、今後とも体制の充実等を含め検討してまいります。
手話言語条例制定後の取組について
【問】平成30年3月に大阪府で3番目に手話言語条例を制定していただき、7年がたちました。この条例制定の際、今後は施策の推進方針に基づき、市民や事業者向けの出前講座や夏休み手話教室の開催など様々な手話の普及・啓発活動を行うとのことでした。
昨年の手話言語の国際デーの9月23日には水間寺をテーマカラーであるブルーにして、「小さな世界」の手話コーラスをさせていただきましたが、残念なことに市民の方々の参加が少なかったです。
これからも手話は言語であるということを一人でも多くの方に知っていただく必要があると考えますが、市としてのお考えをお聞かせください。
また、聴覚に障がいがある方によるデフリンピックが日本で初めて東京で開催されます。手話言語条例制定の市として、市民への周知や取組について教えてください。
【答】本市では、ろう者の方々や手話通訳、手話サークルの方々とともに、手話普及イベントを行ったり、小学校の総合学習の時間等にろう者が出向き、ろう者への理解や手話に触れてもらう機会をつくったりしています。また、つげさんが手話をしているイラストを広報かいづかや障害福祉課の送付用封筒に掲載するなど手話に触れていただく機会の創出を図っています。さらに今年5月に、近畿ろうあ者体育大会の卓球競技を総合体育館で開催予定であり、実際にデフスポーツを観戦していただきます。
また、市のイメージキャラクターつげさんを東京2025デフリンピック応援隊に登録し、SNS等での応援メッセージの発信や講演会を開催し、周知を図ってまいります。
このデフリンピック開催を好機と捉え、子どもたちが聴覚障害の方たちへの理解を深める取組を充実させ、「だれもが個性を生かし、力を発揮できる」共生社会への理解をより一層深めることができるよう、教育委員会と連携を図ってまいります。
その他の質問
- 観光施策について
- 子どもの貧困対策について
- こども食堂のさらなる支援充実とネットワークづくりについて
- 次世代教育推進事業について
- 図書館の有意義な改装と使用目的の多様化について
- 終活支援と墓じまいについて
- 南海貝塚駅周辺の都市計画について
- 三館等合同施設整備について
- 地域防災計画について
- 公園整備について
- オンデマンド交通・定時定路線バスの今後について
- 貝塚版ホームスタート事業の導入について
- がん検診受診率アップの取組について
一般質問
第1回定例会3月7日に行われた一般質問の一部を要約し、お知らせします。
高齢者補聴器購入費用助成事業について
《無会派》 小谷真章
- 【問】この助成事業について、利用実績を踏まえ、令和7年度の予算額が縮小されるということです。予算が残っているのであれば、助成対象を市民税非課税世帯に限定せず、所得制限を撤廃して、幅広く市民が利用できるものにすべきと考えます。また、助成額の増額なども検討すべきと考えますが、いかがですか。
【答】経済的な理由で、補聴器が必要な方が購入できないということがないように、市民税非課税世帯を対象としており、これを拡大する予定はありません。助成額の増額については、補聴器の価格の動向など、引き続き調査したいと考えていますが、現段階で変更予定はありません。 -
【問】補聴器については、サブスクリプションという方法も始まっていますので、研究をしてはいかがですか。
【答】まずは情報収集に努めたいと考えています。
【その他の質問】
大阪・関西万博への遠足について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
貝塚市議会事務局
電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階
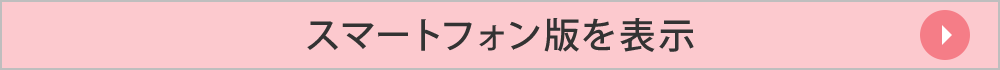








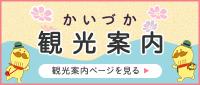
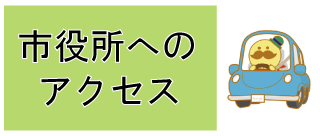

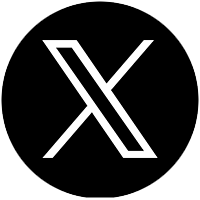


更新日:2025年05月02日