2,3ページ
一般質問から
第4回定例会(12月2日、3日)に行なわれた一般質問のうち、その一部を要約し、お知らせします。
自転車用ヘルメット着用の啓発について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》蓮池陽佑
- 【問】法改正により自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。本市でのヘルメットの着用率を教えてください。
【答】令和5年の大阪府警の調査では、貝塚市のヘルメット着用率は5.4%でした。 - 【問】ヘルメット着用の啓発状況を教えてください。
【答】広報紙やポスター掲示による周知に加えて、関係機関と連携し、交通安全運動期間中のヘルメット着用キャンペーンなどで呼びかけを行っています。また、毎年小学3年生を対象とした自転車を使った交通安全教育において、頭部を保護することの重要性について説明するなど、周知拡大に努めています。 - 【問】大阪府警が啓発動画を作成しています。保護者が集まる機会に上映したり、情報誌面で動画の情報提供を行うなど啓発してはいかがですか。
【答】保護者が集まるPTA総会などの開始前に上映したり、参観日等の際に玄関にあるモニター等で放映したりするなど、各学校園にて可能な方法で活用するよう校園長会等を通じて伝えてまいります。また、教育委員会発行の機関紙に記事を掲載し、その中で、動画のURLやQRコードを紹介してまいります。
- 【その他の質問】
大阪広域データ連携基盤の活用について
ワーケーションの推進について
都市計画道路泉州山手線について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》中川剛
- 【問】泉州山手線が開通することで、例えば騒音対策など周辺住民の不安や課題があると思います。市として、このような声をしっかりと把握し、大阪府と協力して対策を行うべきと考えますが、いかがですか。
【答】大阪府が地元町会で開催した説明会に本市も参加し、各町会の現状、要望等の把握に努めています。本市では、大阪府と定期的に泉州山手線連絡調整会議を開催し情報交換などを行っており、地域の方からの環境が変わることへの懸念や、高架下の利用など、大阪府と共有を行い、引き続き連携し事業推進に努めてまいります。 - 【問】地元の自治会の方から高架下を使いたい、トイレを設置してほしい︑高井城址をそのままの形で残したいといった要望があった場合、しっかりと大阪府に届けることが重要だと思います。そういった要望に対して、積極的に関わっていただきたいと思いますが、いかがですか。
【答】地元町会からの様々な要望につきましては、具体的な利用目的などが明確になった段階で市にご相談いただければ、大阪府に要望を伝え、協議を行ってまいります。
- 【その他の質問】
デマンド交通の実証実験について
マイナンバーカードの普及と利用促進・活用について
病児保育受け入れ施設のさらなる充実を図るための支援について
学校における安全対策について
《無会派》小谷真章
- 【問】学校安全対策事業として行っている小学校の受付員の配置時間を削減する計画があるとのことですが、理由を教えてください。
【答】今年度、職員室等から開閉できる電子錠付きの正門、モニター付きのインターホンおよび防犯カメラを整備します。これに伴い、普段の来客対応は職員室等からモニターで確認して行い、令和7年4月から正門が開いている登下校の時間帯のみ受付員を配置することを検討しています。また、土曜日や夏休みなどの学校休業日も受付員を配置しない予定です。 - 【問】お答えいただいたのは、どのように削減するかということです。なぜ削減するのか理由を再度教えてください。
【答】子どもたちを安全に登校させた後は、門を閉めて安全を確保し、来客は学校が対応します。幼稚園はすでにそのようにしているので、小学校も同じ対応にしていきます。 - 【問】保護者、教職員の意見を聞かず、一方的な決定だと感じますが、いかがですか。
【答】門を閉めることで、子どもたちの安全は確保できると考えています。今後も子どもたちの安全を見守ってまいります。
- 【その他の質問】
統合型校務支援システム導入について
大阪・関西万博への遠足について
グレーチングの補修、整備について
図書館における宅配サービスについて
学童保育(留守家庭児童会)について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》中西真知子
- 【問】今年度に生じた低学年の待機児童の問題を受け、令和7年度において待機児童が生じた場合の対策として、どのような対策を準備しているのでしょうか。
【答】低学年の待機児童解消の対策は必要と考えています。今年度は受け入れ可能な仲よしホームへのタクシー送迎で対応していましたが、本来は自校で受け入れるべきという考え方もありますので、学校の空き教室の利用について学校と調整するなど、可能な限り自校の仲よしホームで受け入れができるよう対策を検討しています。 - 【問】学童保育の開設時間について、小学校の長期休暇や土曜日など、現状の8時30分よりも早い時間での開設ができないものかとこれまで質問してきました。改善する予定はありますか。
【答】開設時間は、土曜日や小学校の長期休業中は8時30分のため、保護者にとっては平日と同じ時間に子どもを送り届けることができない状況にありました。令和7年4月から8時開設とする予定です。 - 【問】開設時間の変更により、保護者の負担金の増額は行うのでしょうか。
【答】子育て支援という観点からも、現時点で負担金の増額は考ていません
- 【その他の質問】
子どもたちの学校生活と教育環境について
子どもたちの居場所について
職員の病気休暇・早期離職に対する対策と人事院勧告に基づく対応について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》八野裕嗣
- 【問】メンタルの不調に陥る職員が増えているが、職員を守るための職場のフォローはどうなっていますか。
【答】管理職によるマネジメントが重要と考え、全管理職を対象とした研修を実施しています。 - 【問】今年8月に発出された人事院勧告には、業務量の偏りの是正、キャリア支援などが重要とされているが、どのような対策をされているか。
【答】業務量の偏りの是正については、労働時間の平準化等を目的として、昨年度から職員登録型応援制度を実施しています。キャリア支援については、同じ所属で4年を迎える者を対象に実施する人事異動自己申告書に加え、今年度から対象者以外からも人事に関する意見を聴く機会を設ける予定です。 - 【問】有能な人材の獲得および離職防止のためには、「フレックス制度」「カムバック制度」「テレワーク制度」などの多様な働き方の実施も有効と考えますが、いかがですか。
【答】現在、これらの制度の導入は考えていませんが、人材確保のための有効な取組として、他市の状況等も注視しながら研究したいと考えています。
- 【その他の質問】
マイクロカプセル等による海洋汚染対策と啓発について
少子化対策としての結婚支援等について
貝塚地域ブランド推進協議会について
観光施策について
《公明党議員団》前園隆博
- 【問】長期滞在を促し、インバウンド需要を確実に取り込むため、宿泊事業者が体験型観光提供事業者と連携して日本文化等の体験型観光を推進しているところがありますが、検討してはいかがですか。
【答】例えば、本市を訪れた方に着物を着ていただき、古民家などで日本庭園を見ながら、和菓子と日本茶を味わっていただくなど、特別な空間を感じていただける体験型コンテンツが造成できないか貝塚地域ブランド推進協議会で検討しているところです。 - 【問】旅行、観光などで現地を訪れた方がその場で寄附を行い、返礼品として宿泊施設利用補助券、施設利用券などを受け取るふるさと納税が注目されています。ふるさと納税の本来の目的である地域に対する興味や関心、共感を持って寄附が行われることだと考えますが、いかがですか。
【答】本市に共感を持った方が即座に寄附をしていただくことができ、再び本市を訪れたいと感じていただけるきっかけになるサービスであると考えています。一方で、その決済サービスの利用について同意をいただける返礼品提供事業者の協力が不可欠ですので、返礼品提供事業者の声を聞きながら、導入について検討したいと考えています。
- 【その他の質問】
高齢者などへの交通支援について
GIGAスクールについて
二色の浜パークタウンの中央緑道のせせらぎの復活について
《無会派》阪口勇
- 【問】二色の浜パークタウンのせせらぎの循環ポンプが、数年前に故障し、多くの方から復活させてほしいという声があります。故障から3年以上経過していますが、復活させる考えはないのでしょうか。
【答】既存施設の更新や維持管理のための予算確保が大きな課題となっており、優先順位をつけて整備改修をせざるを得ない状況にあります。市域全体での持続可能な公園の維持管理手法の調査研究の中で、当該せせらぎについても検討したいと考えています。 - 【問】新しいものをつくるより、公園など今ある財産の維持管理をしっかりする方が予算が少なく、有効利用ができると考えます。優先順位があることは理解しますが、市長の姿勢が大きく影響すると思いますが、いかがですか。
【答】安全安心に関わる部分や緊急性があるもの、あるいは広く市民に受益があるのかということで優先順位をつけています。また大きな額の改修を行う場合は、国の補助金が得られるかということもありますが、この件では獲得は難しいと考えています。
- 【その他の質問】
人口減少対策、住みよい貝塚づくりについて
帯状疱疹ワクチン接種費用の助成について
《公明党議員団》堺谷裕
- 【問】国は、令和6年6月に帯状疱疹ワクチンを定期接種に含める方針を決めました。今後、接種の対象年齢など専門家会議で議論した上で正式に決定するとのことですが、現在、貝塚市における帯状疱疹ワクチン接種費用助成について、どうお考えでしょうか。
【答】現在、帯状疱疹ワクチン接種は、予防接種法に基づき公費負担される定期接種ではなく、個人の希望と医師の判断によって接種する任意接種に位置付けられています。本市では、定期接種に含まれないワクチン接種の費用助成を行う予定はありません。しかし、今後、国の動向を注視し、帯状疱疹ワクチンが定期接種化されたときには、遅滞なく接種費用の助成ができるよう準備を進めてまいります。 - 【問】大阪府大東市は、令和7年1月から帯状疱疹予防接種費用助成を実施すると聞いています。本市も大阪府で2番目となる費用助成をしてはと考えますが、いかがですか。
【答】国が定める定期接種には、予防接種法に基づく救済制度が設けられていますが、任意接種の場合は、国の救済制度は受けられません。よって、本市では、帯状疱疹ワクチンが定期接種化された際に、接種費用の助成を行ってまいります。
- 【その他の質問】
高齢者の見守りについて
公用車の使用について
投票率の向上について
《公明党議員団》谷口美保子
- 【問】先日の少年の主張大会で、「多くの人の意見を反映するための選挙なのに、選挙に行っている若い人が少ないと一定の年齢層だけの意見で決まってしまうのではないか、一人ひとりが大切な意見を持っているはずで、それを伝えないともったいない。」と小学生が主張していて、すごいなと思いました。現在の小・中学校における主権者教育の現状をお聞かせください。
【答】小学6年生の社会科と中学3年生の公民分野に政治についての取り扱いがあります。小学校では、係などのリーダーを決める際に、選挙について学習したことを生かしたり、中学校では、実際にマニュフェストを考えさせた上で模擬選挙を実施した例もあります。 - 【問】議会のライブ配信や録画配信の視聴等を取り入れた具体的な主権者教育が必要だと思いますが、いかがですか。
【答】一部の中学校では視聴を授業に取り入れています。自分たちが住んでいるまちの身近な課題について議論する市議会の様子を見ることは、主権者としての自覚を育むことや投票率の向上を図る上で有効な手立てであると考えますので、視聴を取り入れた実践について情報提供してまいります。
- 【その他の質問】
つげさんポイントの更なる充実について
電子図書館の導入について
投票率向上への対策ができていない問題について
《自由市民》出原秀昭
- 【問】投票所として借りている耐震化されていない町会館等において、選挙中に災害が起こったときに市民に対して責務を負うのは貝塚市だと考えますが、いかがですか。
【答】投票所として、耐震性を満たしていない町会館等を借りて、選挙を行っているときに、万が一、大きな災害が起こって建物が壊れるなどした場合の市の責任については、法律相談をした上で、見極めたいと考えています。 - 【問】投票立会人の報酬が1日1万3千円では、少ないと思います。町会長は、他の方にお願いするにはあまりにも安すぎるので、お願いすることができず町会長自らが投票立会人になることが多いと聞いています。投票立会人の報酬を上げてほしいと思います。市では決めることができないということですが、誰が決めるのですか。
【答】選挙管理委員会に諮って決定しています。 - 【問】では、選挙管理委員会に諮って報酬を上げてほしいと思いますが、いかがですか。
【答】現時点では考えていませんが、投票立会人報酬のあり方について、各市の考え方を確認したいと考えています。
- 【その他の質問】
南海貝塚駅周辺の再開発が進んでいない問題について
大阪・関西万博について
職員人事について
都市計画道路泉州山手線における官民連携について
「オーガニックビレッジ」について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》長谷川博文
- 【問】オーガニックビレッジとは、有機農業の生産から消費まで一貫して、農業者のみならず、事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村のことを言います。貝塚市内には有機農法に関心のある生産者が多く、有機農業を広げていく土壌は整っています。オーガニックビレッジ宣言することで消費者、生産者ともに大きく意識が変わると思いますが、いかがですか。
【答】オーガニックビレッジ宣言は、有機農作物の生産、流通、加工から消費まで、生産者やJAなどの関係者の一貫した体制づくりが必須であり、現時点では宣言をする考えはありませんが、今後も生産者やJAなどの意向並びに国や他の自治体の動向を注視してまいります。 - 【問】貝塚市の農業者は、気概を持って農産物に付加価値をつけたいと思っていますので、宣言をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
【答】オーガニックの農産物は少し値段が高くなることもあるので、消費者が積極的に購入するという意識もある程度根付く必要があります。生産者やJAだけでなく消費者も含めて雰囲気の醸成に努めたいと思っています。
- 【その他の質問】
BCP(業務継続計画)について
困難な問題を抱える女性への支援について
《新政クラブ》南野敬介
- 【問】困難な問題を抱える女性への支援について、相談窓口を教えていただけますか。
【答】人権政策課で受け付けています。複合的問題を抱えていることが多いことから、庁内関係部署や関係団体と連携し、適切な支援担当へつないでいます。 - 【問】法律に「市町村は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。」とあります。本市の状況を教えてください。
【答】女性相談支援員の役割を担うものとして、女性カウンセラーによる女性相談を月2回実施しています。 - 【問】月2回の女性相談では、緊急を要する相談に対応できないと思います。専門知識を持った常駐の相談員を配置すべきと思いますが、いかがですか。
【答】市民相談室でも専門的な分野の相談員を配置し、いろいろなご相談を受け、対応できていると考えていますが、相談しやすい環境をつくる必要があると認識しています。 - 【問】相談員の人材の発掘、また職員の研修を積み上げていくなど、全庁的に取り組んでいくべきだと思いますが、いかがですか。
【答】市民に寄り添った相談体制がとれるように努めてまいります。
- 【その他の質問】
高齢者運転免許証自主返納支援事業について
過去の一般質問や委員会質問における、その後の進捗などについて
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》樽谷 庄道
- 【問】寺内町の景観重点地区指定に向けた地域住民との合意形成にどのように取り組んでいますか。
【答】地域からの景観重点地区に指定してほしいという声を受け、貝塚市景観審議会において、必要性、効果性、そして地元住民の自発的な活動や意向などに基づく実現性を踏まえて、景観重点地区に指定するかを判断します。まずは地域の総意として、この地区を指定してほしいというご意見が大事だと考えています。 - 【問】地域住民やボランティアによる活動支援、コミュニティ形成を通じた地域活性化と魅力向上を目指すとのことですが、具体的な進展や課題、新たな施策の検討状況について、お伺いします。
【答】観光振興ビジョンに基づき「かいづか観光×まちづくりワーキング」を実施し、ワーキング参加者同士の連携による事業の造成など、地域活性化や経済活動にもつながる場の提供を行っています。引き続き、地域での活動を支援し、地域活性化と魅力向上に努めるとともに、例えば水間門前町のように、寺内町においても地元が主体となって地域活性化や魅力向上の機運がさらに高まることを期待しているところです。
小学校の受付業務について
《自由市民》田畑庄司
- 【問】小学校の正門について、モニター付きのオートロックを整備し、受付員の配置時間を短縮すると聞いています。子どもは貝塚市の宝なので、安全確保のためにもこれまでどおり受付員の配置を継続していただきたいと思います。小学校の登下校の対応については、他の議員も質問しているので、私からは学童保育についてお伺いします。保護者が迎えに来たときの対応はどのようにするのですか。
【答】各ホームの指導員が、インターホンやその子機のモニターで保護者を確認し、電子錠を開錠する対応を考えています。 - 【問】保護者への説明も必要だと思いますが、いかがですか。
【答】毎年、説明会を開催させていただいており、その機会に丁寧に説明させていただきたいと考えています。 - 【問】保護者からもいろんな意見が出ると思いますが、きちんと対応してもらえますか。
【答】ご意見、ご要望についても、対応できる部分は対応したいと思います。
- 【その他の質問】
市役所駐車場について
遺族会について
町会・自治会について
市役所の食堂について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
貝塚市議会事務局
電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階
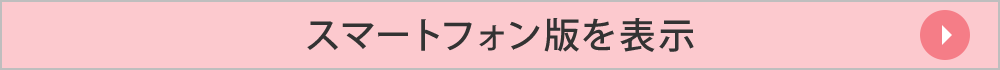








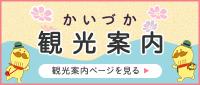
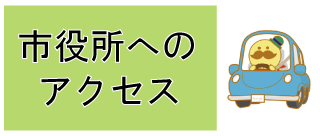

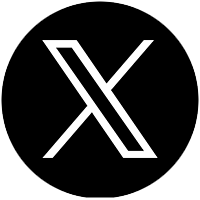


更新日:2025年02月04日