2,3ページ
一般質問から
第3回定例会(9月5日、6日)に13名の議員が一般質問を行いました。その一部を要約し、お知らせします。
一般質問は、一問一答式か一括質問式を選択し、市政全般について質問できます。
制限時間は、60分となっています。
8050問題・親亡き後問題について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》蓮池陽佑
【問】親亡き後問題の大きな課題である財産管理と身上監護に対しては、成年後見制度の利用も有効だと考えます。国の第2期成年後見制度利用促進基本計画の中で、各自治体は、令和6年度中の中核機関の設置が努力義務となっていますが、進捗はどうですか。
【答】令和7年10月に設置を予定しています。現在は、中核機関を設置するにあたり必要な事項を検討することを目的とする準備委員会の立ち上げに向け、委員の構成や所掌事務等について関係機関と協議を行っているところです。
【問】障害のある子を支える親にとって、将来その子を支えられなくなったら、その子の支援やサポートを誰がどのように引き続き担ってくれるのかという漠然とした不安や心配が最も切実な問題になっています。成年後見、任意後見、民事信託等にはそれぞれ特徴があり、課題も問題も千差万別の中でどれか一つの制度の利用で、問題を解決できるわけではありません。選択肢を広げて適切な方法で制度を組み合わせて活用することで課題解決に向けて進むことができると考えます。
任意後見、民事信託制度等の利用を考えている方への相談対応等のサポートを検討すべきだと思いますが、いかがですか。
【答】先ほどの準備委員会で検討したいと考えています。
その他の質問
大阪・関西万博について
学童保育の待機児童ゼロの取組について
《無会派》阪口勇
【問】来年度、学童保育の待機児童を出さないためには、予算が必要で、先延ばしできない問題ですので、前回に引き続き質問します。今年、南小学校で低学年の待機児童が多く出ていますが、次年度の見込みはいかがですか。
【答】来年度の入学児童数は、今年度よりも減少する見込みです。待機児童が出ないと言い切れないですが、今年同様、タクシー送迎等で空きのある仲よしホームでの受け入れを検討したいと考えています。
【問】待機児童となった場合、親は仕事を辞めなければならないこともあります。
今年、南小学校の待機児童は、1年生から3年生で10数名です。来年度以降も待機児童が出ることを見越して、現在2クラスのところ指導員を追加して、3クラスにする努力をすべきではないですか。
これまで、貝塚市は自校で学童保育を行い、待機児童を出さない対策をとってきました。今から次年度待機児童が出るとタクシーで空いている仲よしホームに送ることを選択肢に入れるのではなく、1クラス増やすよう対策すべきではないですか。
【答】待機児童が出ること自体望ましくないので、どういう対応が実現可能か、その負担をどうするかを考えたいと思います。
その他の質問
地域防災の強化について
認知症の方が安心して暮らし続けられるまちづくりについて
《公明党議員団》谷口美保子
【問】一人でも多くの地域の方が認知症の人に対する適切な接し方を身につけて、認知症の方の行動・心理症状の発生を抑制することは特に重要であると考えます。そのための効果的な技法として「あなたを大事に思っている」ということを「見る・話す・触れる・立つ」の四つの柱で、相手が理解できるように届けるケア技法である「ユマニチュード」が注目されています。これを学び実践した介護現場では、認知症の方の行動や心理症状が改善され、ケアする側の負担も軽減されたとの有効性も報告されています。
認知症の方も命令ではなく、同じ目線で話されると変わってくるというこの技法を一人でも多くの方に知っていただきたいと考えます。
市民講座や認知症サポーター養成講座を受けられている方のスキルアップとして開催してはどうですか。
【答】本市では、認知症について正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り、支援するため、認知症サポーター養成講座を行っており、その講座では、認知症の方と接する上での心構えや、関わり方についても学んでいただいています。
ユマニチュードの技法は、今後どのように活用できるか研究したいと考えています。
その他の質問
子どもたちの意見を市政に反映する事業について
市内の子ども食堂のこれからについて
緊急通報装置について
《公明党議員団》 堺谷裕
【問】近年、独り暮らしの高齢者が増えています。家の中で亡くなる原因はいろいろありますが、緊急時に気づいてもらえるかが大切だと思います。緊急通報装置が設置されていれば、救える命があったのではないかと思います。貝塚市の緊急通報装置を設置されている方からの緊急通報件数を教えてください。
【答】令和5年度は14件、令和6年度は7月末現在8件です。
【問】他市と比べて緊急通報装置の申請基準が厳しいと思いますが、いかがですか。
【答】緊急通報装置は、自宅での急病や災害の緊急時に、ボタン一つで緊急通報先につながる装置で、自宅外に持ち出して使用できないことから、対象者を緊急時に周りに助けを呼ぶことが難しい常時寝たきり、または日中も寝たり起きたりの生活をしている状態の方としています。
【問】今後、申請基準の見直しは考えていませんか。
【答】現在のところ基準の見直しは考えていません。
ただし、地域包括支援センターの職員や、ケアマネジャーなどから、現状について聞き取りを行い、実態把握に努めてまいります。今後も、必要な方に必要なサービスが過不足なく届くよう丁寧に対応いたします。
その他の質問
災害対策について
住宅セーフティネット法と居住支援について
《公明党議員団》前園隆博
【問】平成29年に住宅セーフティネット法が改正されて以降、全国で800を超える居住支援法人が指定されています。居住支援法人は、住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居にかかる情報提供、相談、見守りなど要配慮者への生活支援を行います。本市の状況を教えてください。
【答】今年度、本市域内にある不動産店1社が大阪府より居住支援法人の指定を受けました。今後、機会を捉えて不動産店などの関係事業者に働きかけてまいります。
【問】今回の法改正では、居住支援法人が大家と連携して、日常の安否確認、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅の創設がうたわれていますが、市の考えをお伺いします。
【答】この制度は、大家と要配慮者双方の需要に合致したものであり、現在国において検討されている内容に基づき、適切に対応いたします。
【問】岸和田市では、社会福祉協議会が居住支援協議会の役割を担っています。本市でも居住支援協議会を設置しては、いかがですか。
【答】法改正により、市町村において居住支援協議会設置の努力義務が示されたことから、本市の状況に合った体制を検討したいと考えています。
その他の質問
貝塚市ふれあい収集について
クビアカツヤカミキリの防除について
リチウム蓄電池等の拠点回収について
南海貝塚駅周辺整備について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》中川剛
【問】南海貝塚駅周辺整備については、「南海貝塚駅周辺まちづくり検討および都市計画道路見直し検討支援業務」の公募型プロポーザルによる業者選定を行い、契約を締結し、市民の期待は大きくなってきています。3月定例会の代表質問では、地元町会館などにおいても意見交換会等を開催するとの答弁がありましたが、現在決まっている予定について伺います。
【答】南海貝塚駅周辺のまちづくりに向けた市民説明会につきましては、8月に市役所、山手地区公民館にて説明会を2回開催し、まちづくり検討の経緯、上位計画の位置づけ、整備構想図案等を説明いたしました。また、まちづくりについて市民の皆様のご意見をお聞きするための意見交換会を10月から11月にかけて、市役所、山手地区公民館及び2か所の地元町会館にて合計4回開催する予定です。
【問】令和7年度にまちづくり基本計画を策定するとのことですが、整備計画のスケジュールを示すことにより貝塚駅が変わっていくというイメージが持ちやすく機運醸成にもつながると考えますが、いかがですか。
【答】まちづくりを進める上での長期的な整備計画のスケジュールは、今後策定する基本計画において、お示ししたいと考えています。
その他の質問
平和教育について
里親制度の普及・啓発について
カスタマーハラスメント対策について
市営住宅入居時に保証人を不要にする件について
《無会派》 小谷真章
【問】令和2年に国土交通省から保証人の確保が困難であることを理由に入居できない事態を生じさせないようにすることが必要であるという通知が出されました。大阪府営住宅も保証人が不要となりました。本市でも保証人を不要としてはいかがですか。
【答】貝塚市営住宅条例および施行規則に規定する保証人猶予制度により、保証人が確保できなくても、入居を断ることはしていません。国の通知どおり、市営住宅入居の際に保証人を確保できないことが理由で入居できないといったことはありません。保証人は、滞納解消だけではなく入居者が安心して暮らしていける一つの手段と考えており、現時点では保証人制度は必要と考えています。
【問】保証人の猶予申請の後の追及はしておらず、良心的な運用がされていると思います。今後も、良心的な運用の継続を保障する必要があると思います。市長の任期中は、現在の運用を継続していただけますか。
【答】安定的な運用とするためには、担当者が変わったから対応が変わるという不安定なものではなく、文言として整備しておく必要があると考えますので、検討させたいと思っています。
その他の質問
高齢者補聴器購入費用助成事業について
市内訪問介護事業者の経営状況を調査する必要性について
新型コロナウイルス感染症対策について
日本遺産「葛城修験」の追加認定を受けて
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》長谷川博文
【問】日本遺産「葛城修験」に貝塚市が追加認定されたことを受けてどのような取り組みを考えていますか。
【答】今年度は、日本遺産の認知度を高めるため、懸垂幕やのぼり、ポスター、チラシなどによる市民への周知と、追加認定を受けた3市町共催での市民報告会の開催を計画しています。また12月には、貝塚地域ブランド推進協議会主催で、日本遺産追加認定記念ツアーを実施します。
令和7年度には、市内の葛城修験関係文化財の調査を行い、その成果を郷土資料展示室での展示やかいづか文化財だよりテンプスなどで市民に公開しようと考えています。
【問】葛城修験の追加認定を受けて、今まで以上に和泉葛城山を中心に山手地区への観光客の増加が見込まれます。交通アクセスはどうなっていますか。
【答】現在、水間鉄道・水間観音駅を発着する「は~もに~ばす」が平日に5便・土曜日、日曜日、祝日に6便、蕎原バス停(葛城登山口付近)まで運行しています。さらに水間鉄道・水間観音駅前にはタクシー乗り場が設置されています。
また、来年1月から約1年間にわたって山手地区においてデマンド交通の実証運行を計画しており、実証運行期間中は、平日はデマンド交通(タクシー車両)、土曜日、日曜日、祝日は観光客など、バスの利用者が多いため、現在と同様の「は~もに~ばす」の運行を予定しています。
稼ぐ自治体について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》八野裕嗣
【問】昨年度のふるさと納税額が減っていますが、原因の分析はしていますか。
【答】令和5年度は、令和4年度比で8.2%の減少となりました。原因としては、ふるさと納税制度の改正に伴い、返礼品に対する寄附額を値上げした影響により、改正後10月以降の寄附額が減少したことだと考えています。
【問】「稼ぐ」の代名詞のようなふるさと納税なので、売れ筋の返礼品を貝塚市でも返礼品とするためにはどうしたらいいのか、事業者にどう働きかけ、全国にPRするかなど、マーケティング等の視点も取り入れ様々な観点から分析する必要があると思いますが、いかがですか。
【答】ふるさと納税を活用し、税外収入の確保を図るとともに本市を好きになっていただき、継続的に応援していただく関係人口の増加を図りたいと考えています。
本年8月6日に返礼品提供事業者勉強会を開催し、選ばれやすい返礼品や売れ筋の返礼品などを研究し、新規返礼品開発や既存返礼品の改良を検討しています。
また、地域でしか味わえない体験を提供する体験型の返礼品について、貝塚地域ブランド推進協議会と連携の上、開発を進めています。
その他の質問
青少年学習指導員(チューター)制度の成果と今後の展開について
子育て政策について
生成AIの活用について
市立貝塚病院での面会等について
《自由市民》出原秀昭
【問】コロナ禍から4年半が経過し、現在5類感染症となっています。この状況で、民生委員の方が、入院している単身高齢者に書類を持っていったときに面会を断られたそうです。民生委員など身近な人の面会は、緩和すべきと考えますが、いかがですか。
【答】新型コロナウイルス感染症が拡大する前は、ご近所の方が入院した場合など面会に行くことが社会的に定着していたと思います。それが感染対策で、面会は基本的に制限すると変わりました。5類感染症移行時にも国からは、面会も重要であるが、感染症対策にも留意して行いなさいという指導になっています。
今後、感染症対策とのバランスを踏まえながら、面会機会をなるべく確保できる方向で進めたいと思います。
また、一人暮らしの方や民生委員と連絡を取りたい方など、状況等を十分に勘案しながら面会機会を確保するよう考えたいと思います。
【問】緩和ケア病棟での面会についての対応も改善できますか。
【答】面会は、原則家族、親族としていますが、例えば在宅医療を受けられている方等もございますので、患者様の状況を考慮して対応させていただいています。
その他の質問
職員人事について
南海トラフ巨大地震対策について
投票率向上について
特定健康診査等について
大阪・関西万博の小・中学生見学について
《新政クラブ》南野敬介
【問】大阪・関西万博の小・中学生の見学について、市の方針をお聞かせください。
【答】人権教育を軸としながら、誰一人取り残さない教育の実現をめざしてきた本市としては、全ての児童生徒がこの機会を享受できるよう学校単位での参加を前提に準備を進めてまいります。開催までに安全な環境や条件を確保するとともに大阪府に必要な情報を迅速に提供するよう、引き続き要望してまいります。
【問】私も子どもたちにいろんな体験をさせてあげたいと思いますが、例えば小学校一年生が猛暑の中で移動して事故があってはいけません。万博に行くか行かないかは、各学校それぞれ事情があるので、各学校で判断すべきと考えますが、いかがですか。
【答】教育委員会としては、子どもたちが安全に参加できるよう条件整備に努めています。引率する教職員が不足するのであれば指導主事を派遣するなどし︑参加への可能性を探りたいと思います。その上で学校が参加しないと判断した場合は︑尊重したいと考えています。
【問】教職員の人数も限られていますし、教職員の意見も尊重すべきだと思いますが、いかがですか。
【答】現場の教職員の意見を聞きながら最終的には校長が判断することになります。
その他の質問
成年後見制度利用支援について
犯罪被害者等支援条例の制定について
少子化に対する、貝塚市の考えや方向性について
《大阪維新の会貝塚市議会議員団》 樽谷庄道
【問】児童数の減少により、集団の中で人間関係を築いたり、コミュニケーションの方法を学んだりする機会が減少することが懸念されますが、どのような対策を行っていますか。
【答】学校は教科の学習だけではなく、豊かな人間関係を構築する場でもあります。学校においては、異学年による縦割り活動、幼小連携や小小連携、小中連携における学校間交流等の活動を充実させるなど、様々な交流活動を行っております。
【問】児童数の減少により、一学年一クラスの単学級となることで、人間関係の固定化が懸念されますが、その対策についてはいかがですか。
【答】人間関係の固定化に対しては、例えばいじめ等の問題が生じた際、大規模校のように年度当初のクラス替えにより人間関係をリセットすることはできません。
しかし、6年間同じ集団で学校生活を送ることで、お互いをより深く理解し合うことができます。少人数だからこそ担任だけでなく、多くの教職員が関わることもできます。また、少人数の学校であっても、大規模の学校と同じように、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を配置することにより、問題が深刻化することを防止しています。
その他の質問
災害における貝塚市の備え、啓発などについて
貝塚市職員について
《自由市民》田畑庄司
【問】昨年5月に建築住宅課の職員が、工事未完了にもかかわらず支払いを行い、その後業者が自己破産したため、不適切な会計処理が発覚しました。処分は、本人が減給10分の1を3か月、当時の課長及び課長補佐は10分の1を1か月ですが、部長や特別職の処分はないのですか。
【答】本市職員分限懲戒等審査委員会で審議され、本年7月末に処分を行いました。本件は、組織的な誤りではなく、担当職員による誤った判断により不適切な事務処理がなされたもので、当時の担当部長には訓告相当の判断までとされました。
【問】この審査委員会のメンバーを教えてください。
【答】両副市長、教育長、総務部長です。
【問】内部の職員だけで審査せず、弁護士を入れて審査すべきでないですか。
【答】審査委員会の中で、顧問弁護士に意見を聞くよう指示があり、弁護士にも相談しています。
【問】この件は、新聞に載りましたが、広報には掲載はしないのですか。
【答】迅速に市民周知を行う必要があると判断し、各報道機関への報道提供とホームページへの掲載としました。広報は、月1回の発行で、報道発表から期間が空きすぎるため、掲載していません。
その他の質問
市役所駐車場について
水間公園整備事業について
敬老祝品について
町会・自治会の支援について
市役所の食堂について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
貝塚市議会事務局
電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階
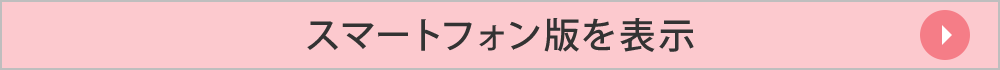








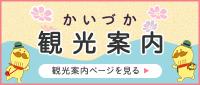
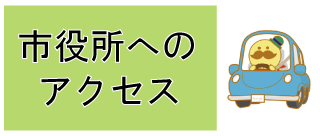

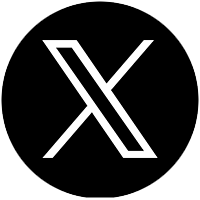


更新日:2024年11月01日