2,3ページ
一般質問
第3回定例会(9月9日、10 日)に行われた一般質問のうち、その一部を要約し、お知らせします。
学校における働き方改革について
《大阪維新の会》中川 剛
【問】教師の本分は質の高い授業を行うことであり、教材の研究や作成等の授業準備は必要不可欠であるにも関わらず、勤務時間内に組み込むことは難しい状況です。児童生徒の学校生活の向上を考え、教職員の働き方改革を実施していくことが大切であると考えます。過去にいくつか提案させていただいた中で、現在、部活動外部指導員の配置及び部活の休養日については、実施していただいてますが、更に多忙化を改めるにあたって、本市の現状と見解をお伺いします。
【答】本市では、警察官OB、スクールソーシャルワーカー等の専門スタッフを中学校に配置し、生徒指導や保護者対応等に学校のチームの一員として参加しています。教員にとって精神的にも心強く、専門的で適切なアドバイスがあり、事態の早期解決が図られ、教員の負担が軽減しています。今年度からは、更に、部活動休養日の設定や部活動指導員の配置もしています。
また10月から、夜間は音声ガイダンスによる電話対応を考えています。音声ガイダンスについては、国の勤務時間上限ガイドラインを踏まえ、教職員の健康管理のため、市として行うものであるという前提で保護者の方にもお伝えしたいと考えています。
今後も教員が教育活動に専念するための支援体制の整備について、検討してまいります。
子ども議会について
《公明党議員団》前園 隆博
【問】1994年に政府が児童の権利に関する条約を批准し、第12条の意思表明権実現の機会を提供するため、全国の地方議会で子ども議会が開催されるようになってきました。子ども議会の開催について、市の見解をお伺いします。
【答】各中学校の代表者が集まる中学校生徒会交流会を平成17年度から実施し、学校をより良くしようと自分たちの身近な課題の解決に向け、意見交流をしています。年々、充実してきており、各校の代表生徒たちの自治意識も育ち、有意義な取組みとして定着してきており、子ども議会については、現在のところ行う考えはございません。
【問】全国各地で行っている子ども議会については、約9割の自治体が子どもたちからの提案・提言に対して何らかの返答を行っていると聞いています。子ども議会について、すぐには無理でも今後検討し、色々な提案・提言を少しでも実現できたらと思いますが、本市のお考えはいかがですか。
【答】本市においては、中学校生徒会交流会等を実施し、大阪府生徒会サミットへも参加しています。そこでは、自分の思いだけではなく、貝塚市のことをはじめ、広く社会の情勢についての提言が含まれているものもあります。これからも本市に関わる内容で、市政に取り入れる参考となるような提案や提言について、必要に応じて取り上げてまいりたいと考えています。
行政が主導する防犯プロジェクトについて
《大阪維新の会》出原 秀昭
【問】市と町会・自治会の補助制度による防犯カメラの設置台数は、今年度設置予定も含めて166台と伺っていますが、行政主導で防犯カメラを設置するには、設置費用とランニングコスト等、費用対効果が重要であります。
「行政が主導する防犯プロジェクト」として、自動販売機への防犯カメラの設置を提案いたします。このカメラは、市内にあるタバコや飲物等の自動販売機に設置します。1台あたりの設置費用は約4万円です。ランニングコストも大幅に下げることが可能で、設置も簡単です。事業主にも設置許可が得やすいのではないかと考えます。市民の皆さん方の安心・安全・見守りを前提に、新たに取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。
【答】防犯カメラは犯罪抑止に大きな効果があると皆が認めるところであります。本市においては、一昨年12月からひったくりの被害ゼロが続いています。要因として考えられるのは、防犯協議会をはじめ、地域の皆さん方が関心を持って見てくれていることが一番大きいと考えます。これは警察の見解ですが、そこにプラスして防犯カメラを設置することにより事件を防ぐことができると考えています。ご提案の安価な費用で防犯カメラを設置できる方法については、調査を進め効果的であれば、検討していきたいと考えています。
自転車の交通安全対策について
《公明党議員団》北尾 修
【問】自転車の交通ルールとマナーをわかりやすく伝え、更に危険予測力を養う自転車シミュレーターという教育機器があり、学生から高齢者まで、幅広い年代に有効な講習だと考えます。本市でも検討されてはいかがですか。
【答】ご提案の機器を購入する考えはありませんが、府が市町村に対し、貸出しを行っています。今年度の申込受付は終了しましたが、来年度以降の活用に向け、関係団体を交え、検討してまいります。
【問】高齢者が自転車の交通事故に関係するケースが多いので、高齢者への自転車安全教室を本市でも積極的にされてはいかがですか。
【答】老人クラブを対象に高年者交通安全リーダー研修会を年1回開催しており、今後は講習等に高齢者の自転車事故に対する視点も取り入れたり、自転車に特化した講習もできればと考えますので、交通安全協会及び貝塚警察署と協議を進めてまいります。
【問】法的効力はないですが、取得をきっかけに自転車の交通ルールを知ってもらう目的で、自転車運転免許証を発行する自治体が増えています。学校現場での自転車運転免許証を取り入れた講習を検討されてはいかがですか。
【答】自転車運転免許証の発行は考えていませんが、受講証等の発行については、実施している他市を参考にしながら研究してまいります。
同性パートナーシップの導入について
《新政クラブ》南野 敬介
【問】平成28年から、性的マイノリティーをテーマに取り上げた研修や広報は、年1回から2回くらい取り組んでいるということですが、当事者の方から、もっと積極的に同性パートナーシップ制度の導入に取り組んでくれたらありがたいというご意見が寄せられています。
この制度について、市政運営方針の中でも研究するということでしたので、その導入の時期も含めてどこまで検討できているのかお聞かせ願います。
【答】制度の導入に向けて、性的マイノリティーに関する啓発と理解の促進が重要であるとの考えのもと、市民に対してセミナーの開催や広報紙への記事掲載に取り組んできました。
今後、市として性的マイノリティーを支援するための機運をさらに醸成し、取組みの方向性を確認しながら各部署でできることをまとめあげる等、総合的な取組みを実施し、同性パートナーシップ制度については、今後2年を目途に導入をめざしてまいりたいと考えています。
【問】今後、制度導入に向けて、啓発や職員の対応等を研究していただきたいと思いますが、例えば当事者の意見や要望があれば、聞いていただく機会を設けていただくことは可能ですか。
【答】聞く機会を設けられたらと考えます。
は~もに~ばすについて
《自由市民》田中 学
【問】以前、「は~もに~ばす」に100円で乗車できたときは、山手地域の木積から市立貝塚病院まで、時間はかかりますが100円で行くことができました。
「は~もに~ばす」の運賃が210円になってからは、乗継券が1回しか発行できないので、黄色区間の「は~もに~ばす」に乗る人たちが、市立貝塚病院まで行くには、片道で420円もかかり、往復では4回も運賃を払うことになり、非常に経済的な負担も大きいと山手地域の人たちからご指摘がありました。
担当課にもいろいろと聞いたところ、水間鉄道を乗り継いでもらったらというようなお話もありましたが、水間鉄道を乗り継ぐとなると、料金が更に高くなりますし、割引の制度もありません。
地域によっては、市役所からもう1度乗り換えないと市立貝塚病院に行けないという現状を、貝塚市としてどのような理解をしているのか、課題を持っているのか教えてください。
【答】「は~もに~ばす」の乗継券を作ったときには、2度乗り継ぐという想定はしていませんでした。
1度乗り継げば、ある程度は希望のところに行けると考えていましたが、このように2度乗継ぎをしなければ、市立貝塚病院に行けないような場合など、それについては対応していきたいと考えています。
防災対策の強化について
《市民ネット貝塚》阪口 勇
【問】阪神淡路大震災や東日本大震災による出火のうち、判明している原因の半数以上を電気火災が占めており、避難する時には電気のブレーカーを落とすことが非常に重要だと考えています。
感震ブレーカーという、地震時に一定の揺れを検知した場合に、自動的に電気のブレーカーを落とし通電を遮断する装置があります。
この感震ブレーカーの設置の促進について、啓発などを行うことが必要だと考えていますが、市のお考えを教えてください。
【答】自宅から避難する際、電気のブレーカーを遮断することは通電火災を防ぐために必要であると考えています。自動で遮断する装置については、9月広報にこのような機械があることを示し、また防災ガイドブックや防災講座などで啓発を行っており、今後も継続して周知してまいります。
【問】いつ起こるかわからない南海トラフ地震のことを考えますと、早急に感震ブレーカーの普及が必要とされていますので、補助金制度を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
【答】感震ブレーカーの必要性というのは認識しており、現物を取り寄せたり、値段を調べたりしております。
また、普及のためにどのような方策があるかということも内部で協議を進めているところです。
障がい者施策について
《公明党議員団》中山 敏数
【問】読書バリアフリー法施行に伴い、地方自治体が取り組むべきポイントは、視覚や発達障がい、肢体不自由等の障がいのある方が読書しやすい環境を整備すること、点字図書や音声読み上げに対応した電子書籍を普及させること等がありますが、本市の取組みをお伺いします。
【答】読書バリアフリー法が施行され、地方公共団体においても視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することとなりました。これまでも本市では、点訳、音訳奉仕員の養成を行い、点訳、音訳図書の充実に努めてきました。今後、国の計画が策定されれば、その内容を踏まえ、事業の実施に取り組んでまいりたいと考えています。
【問】網膜色素変性症という指定難病は、眼の中の光を感じる組織である網膜に異常が起こり、暗いところで物が見えにくい等の症状を発症する遺伝性の病気です。この症状の方が、「暗所視支援眼鏡」をかけると昼間のように明るく見え、日常生活の制限が緩和されるそうです。この眼鏡を、日常生活用具給付等事業の対象にできませんか。
【答】暗所視支援眼鏡については、開発されて間がなく、メーカーが各地で体験会を行っていると聞いています。日常生活用具の給付対象品目については、国が示す要件に加え、用具の効果や近隣他市の状況等を総合的に勘案し、判断したいと考えています。
貝塚市の広報について
《大阪維新の会》牛尾 治朗
【問】スマホで広報紙が見られるアプリ「マチイロ」の導入については、広報かいづか等、貝塚市に関わる情報をすぐに見ることができ、使い勝手が非常にいいものだと思います。この登録について、どのように周知されているのか教えてください。
【答】広報紙アプリ「マチイロ」については、市のホームページや広報紙にQRコードを掲載して登録を呼びかけています。
今後も積極的に啓発していきたいと考えています。
【問】市の公式インスタグラムを開設されましたが、どのSNS媒体を使えば、どの層に訴求できるかを考えていくことが大事だと思います。どのように各SNSを用いた発信情報を決めていますか。
【答】各SNSそれぞれに特性があるので、その特性に応じた活用に努めているところです。
【問】SNSを用いた広報の戦略を練るとなると、専門的知識が必要になってくると思います。そこで、専門人材をある程度活用していくことも一つの選択肢として考えられます。今後、SNSを用いた発信を強化していく考えはありますか。
【答】情報発信をもっと積極的・効果的にすることが大事だと思っています。しかし、今の時点では外部の人材を投入するよりも内部で若い人材の登用などにより、知識を持ち寄りたいと考えています。
幼児教育・保育の無償化実施について
《無会派》明石 輝久
【問】幼児教育・保育の無償化が10月から実施されましたが、副食費の国基準月額4千5百円は無償化の対象からは外されています。
主食費・副食費を全額市の負担にするなど、自治体独自の対応が広がっている中、本市として軽減の対策を検討すべきだと考えますがいかがですか。
【答】10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化に関連して、副食費については、新たに保護者の負担と位置づけられ、国は1ヵ月の副食材料費が、4千5百円程度であれば、給食の質を確保することが可能であると示しております。これを踏まえ、市立認定こども園では、副食費として4千5百円の負担をお願いしたいと考えております。
ただし、年収360万円未満相当の世帯と全ての世帯の第3子以降の園児につきましては、副食費は免除となります。これは国が定めています。
また、副食費については、保育料と同様に減免制度を設ける予定ですので、国の制度設計に基づいて実施してまいりたいと考えています。
【問】今回の子ども・子育て支援法の改正で、国は副食材料費の滞納によって、保育の利用を中断する可能性を示唆しています。この点については十分配慮が必要だと思いますが、いかがですか。
【答】そのようなことは貝塚市では起こりえないと考えています。
市立貝塚病院について
《自由市民》田畑 庄司
【問】市立貝塚病院駐車場の警備員については、長年にわたって何度も質問をしてきました。以前に比べ南海線の最寄り踏切から山側まで渋滞することも少なくなっており、駐車場の警備員は廃止してはと考えますがいかがですか。
【答】警備員の配置については、月曜日から金曜日は午前中を中心に最大4名、土曜日は午前中1名を配置しております。駐車場の拡張工事後は、渋滞の発生もある程度少なくなっていることから、本年11月の契約更新時には、月曜日と水曜日の午前中の渋滞発生時の交通整理に限定して1名の人員配置をするよう見直しを図ってまいります。
【問】医療事務を委託している事業者に対し、事務処理上に誤りがあった際に、どのような指導などを行っていますか。
【答】現在、医事業務につきましては、入院請求、外来請求を含むフロント業務等について、業務委託を行っています。委託事業者が雇用する職員に対して当院に直接の指揮命令権はなく、業務や接遇についての教育・研修は委託事業者が行っています。
しかし、当院として委託事業者の業務の質を確保するため、事務処理上の誤りや患者さんからのクレームについて、随時の報告を受けるとともに、毎月、委託事業者と医事課で会議を行い、当院として改善に向けた指導や要請を行っているところです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
貝塚市議会事務局
電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階
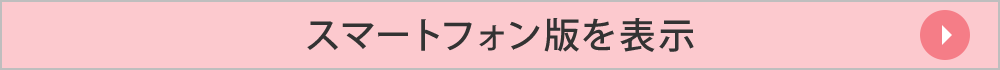








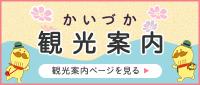
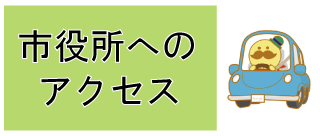

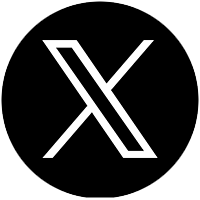


更新日:2019年11月01日