2,3ページ
一般質問から
第2回定例会(6月17日、18日)に行われた一般質問のうち、その一部を要約し、お知らせします。
森林環境税、森林環境譲与税の創設と森林経営管理法の制定に伴う市の役割について
《大阪維新の会》中川 剛
【問】森林経営管理法の第3条に森林所有者の責務として、「森林所有者はその権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」とされております。
一方、市は適切な管理が行われていない森林の特定と所有者の意向調査をし、所有者から市へ経営管理を委託する希望があった場合は、所有者の合意のもと、経営管理権集積計画を定め、経営管理権を設定し、経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者へつなぎます。
林業経営に適さない森林については、市が自ら管理を行い、また所有者不明森林についても、市が管理を行うことになります。
その為にもまず意向調査を早急に進めるべきと考えますがいかがですか。
【答】本年9月に策定予定の大阪府森林整備指針を活用し、本市の森林の区分と保育・管理手法の方針を検討したいと考えております。その後の意向調査につきましては、大阪府が実施する詳細調査の結果に基づき調査対象を選定し、順次実施してまいりたいと考えます。
【問】現段階において、森林組合等と意見交換すべきであると思いますがどうですか。
【答】9月に大阪府の指針が出ますので、それに基づいて話合いをしていきたいと考えています。
交通安全対策について
《公明党議員団》前園隆博
【問】通学する児童の列に車がぶつかる事故は依然としてやみません。子どもの命を交通事故からどう守るのか、対策を急がなくてはなりません。
警察との協議や予算等の関係もあり、すぐに実施することは難しいと考えますが、痛ましい事故を防ぐための努力を怠ってはならないと思います。
交差点など歩行者が待機する場所に、事故時の衝撃を和らげる緩衝具やポールなどの緊急的な措置の検討が必要と考えますが、いかがですか。
【答】交差点など歩行者が待機する場所については、大津市での事故を受けて緊急の安全点検を実施しました。この点検結果に基づき対策を行う必要がある箇所については、警察や地元町会等と協議を行い、交通状況等を勘案し、順次、対策を行ってまいります。
【問】神奈川県川崎市では通学のバスを待つ児童ら20人が殺傷される事件が起きました。
改めて子どもを守る方策が問われています。見守り体制が現状で問題ないのか再点検し、体制を強化する必要があると思いますがいかがですか。
【答】本市では、見守り活動に多くの方が参加されており、登下校の安全確保に努めていただいています。また平成29年度から青色防犯パトロール車を2台に増便し、体制を強化したところです。
今後も関係諸機関と連携を密にし、子ども達の登下校の安全確保に努めてまいります。
高過ぎる国民健康保険料の引下げについて
《無会派》明石輝久
【問】国民健康保険は、憲法第25条に基づく社会保障、住民福祉の制度としての拡充が強く求められています。
本市の基本的な考えについてお伺いします。
【答】国民健康保険は、他の医療保険に加入していない住民を対象とする国民皆保険制度の基礎であり、公的医療保険のセーフティネットであると認識しています。
また、社会保険制度の精神のもと保険制度の枠内で支え合っていくものであると考えています。
【問】独自減免の維持も含めてどういう形で負担軽減を図っていくのか、その方針についてお伺いします。
【答】統一保険料については、6年間の激変緩和措置があります。貝塚市は独自の減免については継続し、国に対して独自減免をするための財源補填等の要望を行っています。
国民健康保険中央会や大阪府国民健康保険団体連合会においても、積極的な意見を述べたいと考えています。
【問】国民健康保険料の本市独自の軽減策を取りながら抜本的に改善を図っていくという努力を更にもう一段、二段と強めていただきたいのですがいかがですか。
【答】医療保険の最後のセーフティネットである国民健康保険制度がもう少し住民本位の制度となるように、これからも国に働きかけるなど努力していきたいと思います。
橋本地区の整備について
《自由市民》食野雅由
【問】JR和泉橋本駅からせんごくの杜までは、広い範囲で市街化調整区域があり、近隣商業地域からいきなり市街化調整区域になるという、駅前にしては全国的に珍しい整備の遅れた地域であります。
しかしながら、近年は地元の土地所有者の中で、徐々に開発の意識が高まってきており、昨年7月に橋本町会において、開発の勉強会が始まりました。町会員を対象に数回にわたり開催しており、市にも協力をお願いしているが、現在の進捗はいかがですか。
また、今後、地元としてどう進めていけばよいのか。そして、市からどのような協力を得られるのかお伺いします。
【答】市による金銭的な支援は考えておりませんが、地元からの要望を受け、先般、まちづくりに対する助成事業を行っている大阪府都市整備推進センターに現地を視察いただき、計画の概要について説明を行ったところです。
当該助成については、今年度、追加募集を予定されていることから、地元が本助成に応募する際には、助言してまいりたいと考えています。
まずは、地権者を始めとする関係者が、事業スキームや土地の減歩などについて理解し、住民総意として合意形成を図っていただき、その結果申入れをしていただければ、まちづくりの観点から市として支援をしていきたいと考えています。
職員の配置について
《自由市民》田中学
【問】数年前に会計管理者を課長級にし、部長職の数を減らしたことがありました。
近年、議会からの要望もあり、健康子ども部が増設され部長職が増えましたが、同じ部長級の参与という職が非常に増えてきているというのはいささか疑問に思います。
なぜ増えてきているのか。また外部に部長級を派遣する目的を教えていただけますか。
【答】職務遂行上、より市民本位の政策をするには、人や組織を増やすのではなく、その者の調整能力、調整機能をワンランクアップさせるという意味で参与として配置しています。文化振興事業団に参与級を派遣している一番の目的は、部長会議、庁議に出席してもらい、庁舎建替検討委員会でも直接意見を述べ、議会の意見をスムーズに直接反映できるというメリットが一番であると考え、現職の部長級職員を派遣しています。
【問】職員配置については様々な機構改革も含めて、増える課もあれば減る課もあり、人口の増減や景気動向等を加味して、貝塚市が一枚岩となって進めていかなければならないと思います。今後、新たな事業を創設されるとき等には丁寧な説明をいただきたいと思いますがいかがですか。
【答】参与の配置などの大きな変更については、議員総会において機構改革の説明の際にお話しさせていただきたいと思います。
空き家・空き地対策について
《新政クラブ》南野敬介
【問】木造空き家除却補助制度が4月からスタートしましたが、申請の基準について、かなりハードルが高いと聞きました。
今後もいろいろ検討して利用しやすい制度にステップアップしていく必要があると思いますが、いかがお考えでしょうか。
【答】木造空き家除却補助制度は、法に基づく不良住宅の基準に適合した物件に対する補助をするというものです。当然、その基準に満たないものは補助対象にはなりませんので、市民からの要望が大きければ、国の補助の外枠として何かできるかも含めて検討いたしますが、まずはこの制度を着実に運用させていきたいと考えています。
【問】空き地については処理手順の作業フローを作成し、点数を付け、フローに沿って行っていると思うのですが、数が多いからなのかわかりませんが、対応に時間的なばらつきがあるように思われます。
ある程度期限を決めたフローにしないといけないと考えますがいかがですか。
【答】現在、指導から勧告に至る期限は定めておりませんが、空き地を放置されている方に対して、市として平等な対応をしないと、間違った方向になると思いますので、内規的に何回の指導でその上の段階にいくというところも含めて、検討させていただければと思います。
ドローンフィールドの活用について
《大阪維新の会》牛尾治朗
【問】せんごくの杜のドローンフィールドは、現在、どのような利用促進をしているのかお伺いします。また、様々な団体といろいろな形で協定を結び、活用促進されていると見受けられますが、どのような団体がどういった形で利用していますか。
【答】ドローン測量能力やドローン測量機器の検定及びその練習場所として利活用するため、一般社団法人ドローン測量教育研究機構の協力をいただき、測量に必要な国土地理院の承認を受けた公共基準点や標定用基準点を設置するとともに、空飛ぶクルマの実証実験場としての誘致等、ドローンフィールドの高度利用化に向けた取組みを行っています。
【問】ドローン市場の拡大に応じ、ドローンフィールドを活用していただける関係作りを様々な団体と進めるべきだと思います。ドローン産業の未来を見据え、新たなドローン関連団体との連携協定を模索する方針はありますか。
【答】貝塚市立ドローンフィールドは、ドローンやその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図る目的に設置すると条例で定めています。測量以外にも、空飛ぶクルマの実証実験場としての誘致等、更なる利活用に向け取り組む所存ですので、様々な団体と個別に協議し、協定を結んでいきたいと考えています。
プログラミング教育について
《市民ネット貝塚》平岩征樹
【問】来年度からプログラミング教育が小学校で必修化されますが、基本的な方向性についてお聞かせ下さい。
【答】本市では小学校11 校にICT担当教員を配置しております。そして次年度のプログラミング教育のモデルとなるカリキュラムを提示し、各校が円滑にプログラミング教育を進めることができるような体制を整えております。
【問】プログラミング教育の目的は「論理的思考力を育み、身に付けさせる」ことで、中学校や高等学校でのプログラミング学習に繋がる「気付き」を与える教育が重要ではないかと考えます。
プログラミング教育において、パソコンを使ったプラグドな教育と使わないアンプラグドな教育のバランスについて、お考えをお聞かせ下さい。
【答】プログラミング教育の狙いは、論理的思考を育むこと、コンピューターを活用して身近な問題を解決し、よりよい社会を築こうとする態度を育むこと、各教科等での学びをより確実なものとすることであると考えます。それらの狙いを達成するため、まずは論理的にプログラミングの考え方を育てるアンプラグドでの指導が重要であると考えています。その上でプログラミングソフト等を使い、子ども達が自分達の考えたプログラムをコンピューター上で表現するプラグドの活動も行ってまいりたいと考えています。
通学路等の交通安全の強化について
《市民ネット貝塚》阪口勇
【問】通学路等における車両速度の抑制対策についてお聞きします。住宅地内の通学路等は、制限速度を時速30キロメートルとしている所が多いのですが、中には横断歩道があっても制限速度を超え、通過する車も見受けられます。
学校近くの住宅街の通学路等で自動車の速度を軽減させる工夫が必要だと考えますがいかがですか。
【答】通学路における車両の速度抑制につきましては、徐行などの路面表示による運転者への啓発やゾーン30の導入等について警察や町会と協議を行い、通学児童の安全確保に努めてまいりたいと考えています。
【問】地域では車の速度を落とさせるためにスピードハンプ等の対策を行ってほしいという声も大きくなっています。
通学路等について、車がスピードを出さない道路の構造や路面表示の取組みをより行っていく必要があると考えますがいかがですか。
【答】道路の一部を隆起させるハンプの設置は、二輪車の事故や車両通過時の音の問題もあり、本市として導入する考えはありません。
車両の速度抑制対策では、国が示す事例に路面のペイントによる視覚的なハンプや道幅を狭く見せる方法等もあります。路面ペイント等を一度実験的に設置するというのは、有効性を確認する上では必要だと考えています。
がん対策について
《公明党議員団》北尾修
【問】貝塚市がん対策推進条例第7条では、「教育機関におけるがんの予防につながる学習活動の推進のために必要な施策を推進する」となっています。学校でのがん教育の推進について、本市の取組みをお伺いします。
【答】中学校の学習指導要領では、保健体育科の保健分野において、生活習慣病等の予防の単元で、常習的な喫煙ががん等の疾病を起こしやすくなることを理解できるようにすることなどが求められています。そこで、中学校の保健の授業で、カリキュラムに沿ったがん予防についての取組みを進めています。
【問】がん治療の一つに抗がん剤治療がありますが、その主な副作用として多いのが脱毛です。目に見えるだけに、とてもつらい副作用と言えると思います。がん患者の精神的、経済的負担軽減のためにも、医療用ウィッグ購入費用の助成を検討されてはいかがですか。
【答】本市におきましては、がんのトータルケアを行っている市立貝塚病院で、医療用ウィッグの展示・試着コーナーを設置し、抗がん剤治療の開始前に紹介するなど、心の準備を含めたケアを行っております。
医療用ウィッグ購入費用の助成制度については、市立貝塚病院とも相談し、実施している市の調査を行い、検討していきたいと考えています。
児童虐待防止対策の強化について
《公明党議員団》中山敏数
【問】学校や教育委員会等の関係者が、虐待と疑われる事案に迷いなく対応できるように、文部科学省は「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を作成しました。教育委員会としてどのように取り組まれるのかをお伺いします。
【答】手引きについては、5月15日付で市内全学校園に送付し、教職員に周知したところです。また、貝塚市小中学校生活指導連絡協議会や教育支援センター研究協議会において、本手引きを活用し、学校における日頃の観察や通告の判断など具体的な研修を行う予定をしています。今後も関係機関と連携し、未然防止、早期発見に努めてまいります。
【問】今後、痛ましい事件が起きないように、常にアンテナを張り早期発見に努めていただき、本市の児童相談窓口と子ども家庭センター、また警察等の関係機関との連携強化が大変重要になると思いますがいかがですか。
【答】貝塚警察署との連携や子ども家庭センター、保健所等が参加する、支援が必要な児童の見守りがこれでいいのかを確認しあう会議を増やすなどして、より情報の共有を図ります。
今後も要保護児童対策地域協議会を始めとする児童虐待に関わっている関係機関との情報共有を図り、連携を深め、常にアンテナを張って児童虐待の早期発見に努めます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
貝塚市議会事務局
電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階
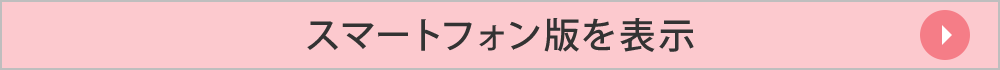








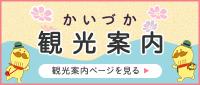
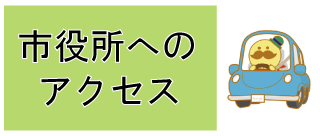

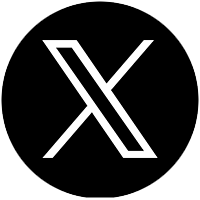


更新日:2019年08月05日