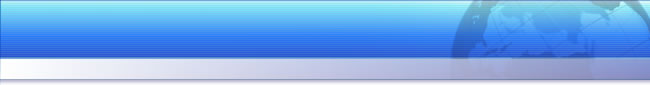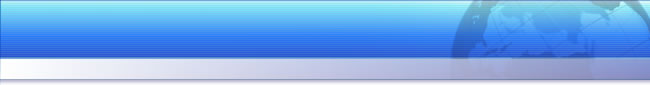| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康子ども部 子育て支援課 |
所属長名 |
岸和田谷 貴浩 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
1 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
2 希望する子育てができる環境をつくる |
| 個別計画 |
貝塚市次世代育成支援行動計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
障害者自立支援法・貝塚市児童福祉法に基づく障害福祉サービスの措置等に関する規則
貝塚市幼児教室要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
就園・就学に向けて、集団生活ができる力をつけ、将来豊かな社会生活を営むことができる。 |
| 具体的内容 |
・利用者(児)に対して児童福祉法に基づき、療育保育に関する児童発達支援
・支援を要する子どもの保育や子育てに悩む親を支援するフォロー親子教室開催
・言語聴覚士・理学療法士による外来訓練(児童福祉法に基づく児童発達支援)
・理学療法士による保育所児への療育アドバイス
貝塚市における就学前児童で発達の遅れや障がいのある乳幼児に対し、心身の発達を促すため幼児教室において、保護者とともに療育・保育を行なう。 |
| 2.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000257 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
02(児童福祉費) |
02(幼児教室運営費) |
01(幼児教室運営事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.25 |
− |
3.23 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
8.2 |
− |
8.46 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
60,300 |
− |
61,384 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
334 |
− |
| 直接事業費 |
3,030 |
1,974 |
2,677 |
2,365 |
1,503 |
| 間接事業費 |
− |
453 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
3,030 |
62,727 |
2,677 |
64,083 |
1,503 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
18,405 |
18,738 |
18,819 |
18,553 |
18,405 |
| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
-15,375 |
43,989 |
-16,142 |
45,530 |
-16,902 |
| 一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
-15,375 |
-16,764 |
-16,142 |
-16,188 |
-16,902 |
| 3.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 児童発達支援を利用した人数 |
人 |
38.0 |
18.0 |
25.0 |
25.0 |
| 児童発達支援の外来訓練利用者数 |
人 |
13.0 |
10.0 |
15.0 |
15.0 |
| 親子教室開催回数 |
回 |
58.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
| 4.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
児童発達支援延べ利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
4050.0 |
維持 |
3091.0 |
2583.0 |
3400.0 |
3400.0 |
| 利用者一人あたりコスト |
千円 |
20.29 |
24.81 |
|
|
| 成果指標2 |
親子教室延べ利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
650.0 |
維持 |
912.0 |
1018.0 |
800.0 |
800.0 |
|
|
|
|
|
|
| 5.事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
完全母子通園を基本としながらも分離保育が可能な場合は、母子分離できるよう利用者のニーズと家庭の実情を踏まえて療育と保護者支援に努めた。 |
| 6.項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的(対象・意図)は妥当か |
妥当である |
|
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
|
| 公的関与の範囲は適切か(市が実施すべきか) |
適切である |
|
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
|
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
やや余地がある |
|
| 住民負担は適切か |
適切である |
|
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
|
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
|
| 7.今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
今後も円滑な運営が行えるように努める。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
C:― |
| 今後の改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策) |
| 平成29年度から実施できるもの |
母子通園が基本であるが、母子分離保育へのニーズの高まりから一定期間(6ヵ月)を目途に母子分離をすすめるよう保育体制を見直す。 |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
引き続き分離保育を検討し、分離保育を基本とできるようにしていきたい。 |
|