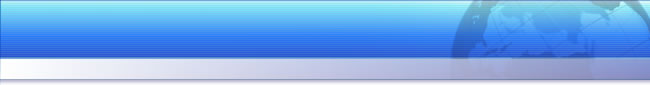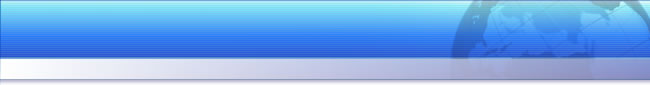| 7.担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的(対象・意図)は妥当か ※1:義務的事業、内部管理事務を除く |
公民館から遠い場所にも公民館の学びを届ける、また、地域活動の活性化のための助言を行うなどで積極的に支援しており、対象・意図は妥当である。 |
関わりの少ない地域へも積極的に働きかけて公民館の学びを広げていく。主体性を発揮できる活動となるよう関わっていく。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切。町会や地域団体の会議や事業に関わることで、地域の課題を共有できる機会にもなっている。現在の体制でできる限りの手段は講じている。 |
自主的な活動の妨げとならないよう関わる。地域の実情に合わせた関わりを行う。また、出前事業として提案できる内容の開拓も行う。 |
| 公的関与の範囲は適切か(市が実施すべきか) ※1 |
地域住民のつながりづくりや地域のつながりづくりを進めていくことは公的に継続して行う必要があり、公民館ができること、地域ができること、と分けて考えるなど、関与の範囲も適切である。 |
地域力の向上につながるよう働きかけを進めていく。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
現状もコストをかけずに実施できるものを用意するなど既に工夫はしており、削減は難しい。 |
他の事業の実施に合わせる等、あらゆる機会を活用するなどでコスト削減を図る。地域の人材活用等の情報収集をするなどで、コストをかけずに効果を上げる方法を探していく。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
取組み始めの地域やある程度自立した地域などそれぞれの段階に合わせた関わりをするなど取り組んでいるが、さらなる利便性の向上や省力化は難しい。 |
町会の状況は様々でまた、変化もしていくが、これまでの蓄積や地域との人間関係も活用しながら効率を高めていく。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
必要に応じて住民負担をしており適切。 |
最初のきっかけづくりに公民館が関わり、自主的な活動につながるよう進めていく。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
予定していた事業は実施できた他、出前事業への依頼も増えてきた。 |
今後も積極的に地域との関わりを広げる中で一層の成果向上を図る。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
出前事業は地域の状況に合わせた内容で実施するなど、事前に地域の状況を十分に聞くことで、ニーズを把握できるよう努めた。 |
日頃からのつながりづくりをしていく。 |