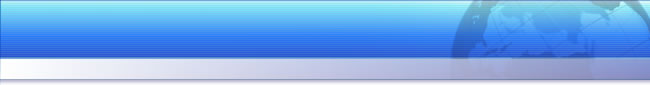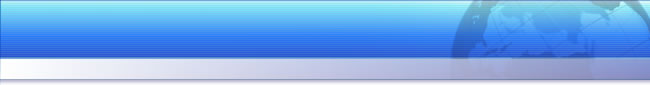| 7.担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的(対象・意図)は妥当か ※1:義務的事業、内部管理事務を除く |
広く市民一般を対象としており、あらゆる人が利用できる施設として運営しており妥当。 |
あらゆる人が利用できる施設として運営できるよう設備面も含め充実させられるよう考えていく。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
クラブや団体など定期利用については一定のルールを定め、より多くの利用ができるよう利用者の協力も得ながら工夫している。 |
部屋の利用が多く、空きが少ない状況の中、講座の時間帯を工夫したり地域を会場にした出前事業も広げていくなどで館内にとらわれない活動を進めている。 |
| 公的関与の範囲は適切か(市が実施すべきか) ※1 |
全ての市民が豊かな生活のための活動の場所として利用できるために、公的関与の範囲は適切である。 |
安全利用や、あらゆる人が利用できる施設にするという点を重視し、継続して運営を行う。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
この事業に関するコストは人件費となっており、コスト削減は難しい。 |
通常の勤務内で運営しており、職員体制を鑑みても削減は難しい。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
公民館の事業や利用について広く市民に知らせる工夫をしていくことで、利便性をあげていく。 |
ロビーや図書スペースについては市民の協力も得ながら活用を広げていく。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
社会教育団体として認められた団体に対して減免制度を適用しており、住民負担は適切。 |
地域活動の活性化や自由な社会教育活動の意識を高めつつ、現状を維持する。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
施設利用回数、利用者共に増加している。 |
利用が集中することも多く、不定期利用の団体に不便が生じないよう定期利用団体との調整を図っていくと共に、利用が少ない時期の活用も検討していく。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
利用希望が集中する場合は希望に添えないこともあるが、利用者の協力を得て調整をはかりできるだけ多くの利用ができるよう努めている。 |
クラブ数も増え、また地域活動の利用も多くなっていることから、利用団体代表者会議やクラブ訪問などで利用者の理解も求めながら調節していく。 |