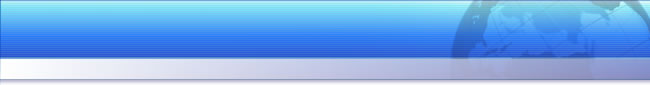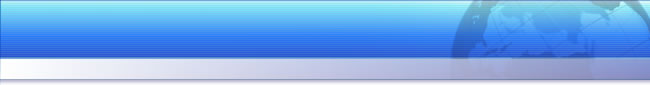| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 学校人権教育課 |
所属長名 |
宮瀧 秀一郎 |
政策
体系 |
総合計画 |
第3章 個性豊かな文化発信都市 |
第1節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
豊かな心を育む教育の充実 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
平成8年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
教育支援センターを貝塚市青少年人権教育交流館に設置している。年間を通じて、不登校や不登校傾向にある児童生徒が、学校に代わり、センターに入室して、学習や体験活動を行うことで、学校への復帰を促している。また保護者に対しては面談や相談に応じている。
|
| 2.事務事業の目的 |
| 対象(働きかける相手・もの) |
不登校及び不登校傾向にある児童生徒 |
| 受益者(誰を・何を) |
市内児童生徒 |
| 事務事業の意図(どういう状態にしたいのか) |
不登校児童生徒の居場所づくりを行う。 |
| 行政の役割 |
不登校児童生徒の理解と、早期の学校復帰を図る。また、不登校児童生徒の保護者からの相談等に応じる。 |
| 3.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000511 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
01(教育総務費) |
03(教育指導費) |
05(教育支援センター事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.17 |
|
0.18 |
|
| 嘱託員数 |
|
1.11 |
|
1.11 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
4,551 |
|
4,609 |
|
| 間接人件費 |
|
543 |
|
617 |
|
| 直接事業費 |
895 |
795 |
879 |
760 |
1,935 |
| 間接事業費 |
|
35 |
|
103 |
|
| フルコスト |
895 |
5,924 |
879 |
6,089 |
1,935 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
895 |
5,924 |
879 |
6,089 |
1,935 |
| 一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
895 |
795 |
879 |
760 |
1,935 |
| 4.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 教育支援センターの職員人数 |
人 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 5.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
教育支援センターに入室した児童・生徒数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
|
減少 |
6.0 |
12.0 |
5.0 |
|
| 市内の児童生徒一人あたりのコスト |
円 |
671.0 |
671.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 6.事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績(昨年からの改善状況) |
| 平成25年度 |
教科指導による学力保障だけでなく、校外での学習機会なども設け、より充実した活動を行っていく。 |
教科指導による学力保障だけでなく、校外での学習機会なども設け、児童生徒がより主体的に活動できるようにした。中学3年生2名は、高校進学につながった。 |
| 7.担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的(対象・意図)は妥当か ※1:義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である。 |
不登校生の居場所づくりとしての教育支援センターは必要不可欠である。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
おおむね適切である。 |
入室者に対して、コストはかかるが、義務教育の意義と教室の特性から考えるとやむを得ない。 |
| 公的関与の範囲は適切か(市が実施すべきか) ※1 |
適切である。 |
義務教育の意義から考えても、教育支援センターはなくてはならない。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
まったくない。 |
入室する児童生徒の性質上、これ以上の職員の削減はできない。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
まったくない。 |
入室する児童生徒は少数であるが、子どもたちに適切に関わるためには、これ以上の削減はできない。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
おおむね適切である。 |
少数の入室者に対してコストはかかるが、義務教育の意義と教室の特性から考えると、市内に教育支援センターがあることの意義は大きい。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上している。 |
不登校の中学3年生が高校に進学できたことは、教育支援センターの役割によるものであり、教育センターの存在はなくてはならないものである。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
おおむね応えている。 |
不登校生がひきこもりにならずに活動できる場として、教育支援センターの果たす役割は大きい。 |
| 8.今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策) |
| 平成26年度から実施できるもの |
より充実した活動を行うため、校外での学習機会を増やしていく。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
中学校と連携しながら、入室者の進路保障面などをより充実したものにしていく。 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
不登校児童生徒の居場所づくりは重要であり、今後とも本センターの必要性は変わらない。自己有用感を高める取り組みを充実させる必要がある。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|