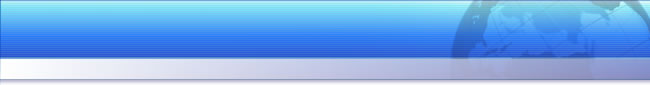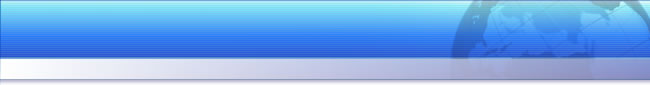| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 児童福祉課 |
所属長名 |
三味 良一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第2章 安全・安心の健康福祉都市 |
第2節 安心して子育てができる環境の整備 |
| 基本計画 |
(2)子どもを大切にする社会づくり |
施策 |
子どもを大切にする社会づくり |
| 個別計画 |
貝塚市次世代育成支援行動計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
障害者自立支援法・貝塚市児童福祉法に基づく障害福祉サービスの措置等に関する規則
貝塚市幼児教室要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
・利用者(児)に対して児童福祉法に基づき、療育保育に関する児童発達支援
・支援を要する子どもの保育や子育てに悩む親を支援するフォロー親子教室開催
・言語聴覚士・理学療法士による外来訓練(児童福祉法に基づく児童発達支援)
・理学療法士による保育所児への療育アドバイス
貝塚市における就学前児童で発達の遅れや障がいのある乳幼児に対し、心身の発達を促すため幼児教室において、保護者とともに療育・保育を行なう。 |
| 2.事務事業の目的 |
| 対象(働きかける相手・もの) |
心身の発達に遅れや障がいのある就学前児童およびその保護者 |
| 受益者(誰を・何を) |
心身の発達に遅れや障がいのある就学前児童およびその保護者 |
| 事務事業の意図(どういう状態にしたいのか) |
就園・就学に向けて、集団生活ができる力をつけ、将来豊かな社会生活を営むことができる。 |
| 行政の役割 |
早期療育により、個々に必要な発達の力をつけ、集団のなかで生活する意欲、楽しさを育む。
子どもの発達についての悩みや相談を受け保護者を支援していく。 |
| 3.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000257 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
02(児童福祉費) |
02(幼児教室運営費) |
01(幼児教室運営事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
3.17 |
|
3.19 |
|
| 嘱託員数 |
|
8.0 |
|
8.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
52,075 |
|
54,742 |
|
| 間接人件費 |
|
732 |
|
867 |
|
| 直接事業費 |
1,694 |
1,397 |
2,427 |
5,164 |
2,236 |
| 間接事業費 |
|
39 |
|
259 |
|
| フルコスト |
1,694 |
54,243 |
2,427 |
61,032 |
2,236 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
18,280 |
18,909 |
19,671 |
17,739 |
18,988 |
| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
-16,586 |
35,334 |
-17,244 |
43,293 |
-16,752 |
| 一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
-16,586 |
-17,512 |
-17,244 |
-12,575 |
-16,752 |
| 4.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 児童発達支援を利用した人数 |
人 |
38.0 |
37.0 |
25.0 |
25.0 |
| 児童発達支援の外来訓練利用者数 |
人 |
18.0 |
11.0 |
15.0 |
15.0 |
| 親子教室開催回数 |
回 |
62.0 |
60.0 |
62.0 |
62.0 |
| 5.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
児童発達支援延べ利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
4050.0 |
維持 |
3342.0 |
3016.0 |
3400.0 |
4050.0 |
| 利用者一人あたりコスト |
千円 |
16.23 |
20.24 |
|
|
| 成果指標2 |
親子教室延べ利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
650.0 |
維持 |
779.0 |
899.0 |
800.0 |
650.0 |
| |
|
|
|
|
|
| 6.事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績(昨年からの改善状況) |
| 平成25年度 |
理学療法士巡回相談
障害児相談支援事業
親子教室相談 |
公立保育所や、必要のある私立保育園から理学療法士が相談を受けている。又、施設内での療育・保育相談や、電話などでの相談を受け、子どもや保護者へのフォローを行っている。 |
| 7.担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的(対象・意図)は妥当か ※1:義務的事業、内部管理事務を除く |
障害のある又はそのおそれのある子ども達の為に様々な取り組みを行い、相談や、アドバイスをしながら保育・療育している。 |
引き続き、ひとり一人に合わせた支援を行う。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である。
それぞれの専門部門においてスタッフを配置し訓練等も実施している。また、保護者や市民からの相談にもその都度応じる事が出来ている。 |
スタッフと訓練の担当者が話し合いながら、個々の支援を進めている。 |
| 公的関与の範囲は適切か(市が実施すべきか) ※1 |
適切である。
民間の施設もあるが、対象児童が増加し、発達の遅れのある子どもにとって就学前は重要な時期でもあり、ニーズに応えるため市が実施すべきである。 |
発達のおくれや障害のある子どもを持つ保護者が身近に相談でき、保育療育を受ける場が必要。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
コスト削減に努めている。
療育に必要な教材などの使用について、有効かつ効果的に療育に取り入れることができているか職員会議等で話し合いエコ運動や、再利用などあらゆる点で節約に努めている。 |
課題なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
利便性の向上に努めている。
保護者の緊急な事態に関して母子分離保育児の長時間保育や一部保護者の自宅待機実施により利用しやすくなっている。また、保護者や市民からの相談にもその都度応じることが出来ている。 |
今後も児童発達支援の中や親子教室などで、発達の事で気になるところや保護者の悩みを相談できたり、一緒に考えていく。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
妥当である。
児童福祉法により算定されている利用者負担額を適用しているが、追跡支援・訓練支援については、2分の1として市独自での単価を設定し、住民負担を軽減している。 |
課題なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
目標値を設定するのは難しいが、数値では表せない成果を向上させている。
家事都合や子どもの体調などに合わせて、無理なく利用して頂けるよう配慮している。その点において利用回数が少なくなってしまうことは仕方ない。
親子教室も増加傾向にあるが、体調により欠席する場合もあるので、目に見えない成果になってしまう。 |
保護者の悩みや子どもに対する思いなど、さまざまな相談を受けながら、個々に対応するようにしている。
その中から成果を数字で表すことはできないが、今後も子どもだけでなく、保護者も含めた支援を丁寧におこなっていく。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
発達の遅れに保護者が悩み、入園する児が増えている。又言語聴覚士における訓練を受けたい希望が増えてきている現状がある。幼稚園児の追跡支援についても就学前のフォローを実施し、保護者支援も対応している。 |
年度によって人数の変動が大きく言語聴覚士は非常勤職員のため回数に制約がある。追跡支援についても親子教室等の利用者に限定せざる負えない。待機の児童が出ないよう工夫していく。 |
| 8.今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策) |
| 平成26年度から実施できるもの |
理学療法士巡回相談
児童発達支援・親子教室相談
市民からの電話相談
障害児相談支援事業 |
| 平成27年度から実施できるもの |
理学療法士巡回相談
児童発達支援・親子教室相談
市民からの電話相談
障害児相談支援事業 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
よりよい保育・療育ができるように幼児教室の充実を図り、障害児の発達支援や親子教室の中で相談業務の充実を図る。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|