 |
| 第92号 安養寺の鉦講 |
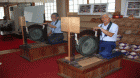 |
|
■仏信仰が盛んであった江戸時代、人々は厚い信仰により宗教行事を大事に守っていました。村人たちは互いに協力しながら行事を執り行うことで、共同体としての結びつきを強めていたと考えられています。 こうした宗教行事のひとつに双盤(そうばん)念仏があります。双盤念仏とは、双盤(鉦)を叩いて節をつけた念仏を唱えるもので、全国の浄土宗寺院で行われています。 平成19年に市内の浄土宗寺院に調査を行ったところ、4つの寺で双盤念仏と鉦講の存在を確認できました。いずれも昭和初期まで行っていたようですが、伝承者の高齢化や戦時中の金属供出により途絶えています。 しかし、名越の安養寺では、詳しく知る人の教えにより戦後に復活させ毎年春と秋の彼岸などに鉦講で双盤念仏を行なっています。双盤は2基あって、2人ずつ計4人が鉦を叩いて念仏を唱えます。1回の演奏は20分程度で、それが終わると和讃(わさん)・回向(えこう)・講話と続きます。 大阪府下で伝承されて残っているのは数少なくなっています。安養寺の鉦講は、本年1月に大阪府の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択されました。 (平成21年3月掲載) |