 |
| 第19号 願泉寺 |
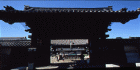 |
|
願泉寺は、通称「なかんちょ通り」と呼ばれている広い通りから50メートルほど北側に入ったところにあります。表門をくぐると正面にどっしりと構えた本堂があり、訪問者を暖かく大きな包容力で出迎えてくれます。ここは「貝塚寺内町」の中心寺院でした。織田信長の石山本願寺攻撃の際には、貝塚寺内の門徒や住民が本願寺に協力。そのため、織田信長は天正5 (1577) 年、和泉へ軍勢を進め貝塚寺内もことごとく焦土と化しました。その後、寺も町も再興され天正11年から2年間、紀州鷺ノ森から顕如(けんにょ)を迎えて本願寺御堂となりました。 願泉寺の名は、慶長12 (1607) 年に本願寺准如(じゅんにょ)から授けられました。本堂・表門・太鼓堂は、貴重な近世建築として平成5年8月に国の重要文化財の指定を受けました。また境内の梵鐘(ぼんしょう)は鎌倉時代のもので、大阪府の指定文化財になっています。 (平成15年2月掲載) |